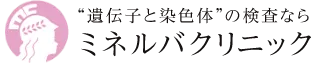疾患概要
CLN1疾患は、一般に乳児型神経性セロイドリポフスチン症(INCL)と呼ばれ、最も早期に発症する形式のバッテン病の一つです。この遺伝性疾患は、主に神経系に影響を及ぼし、乳児期の正常な発達後に重篤な神経退行性の進行を示します。
神経細胞性セロイドリポフスチン症(NCL; CLN)は、遺伝的かつ臨床的に異質な一群の進行性神経変性疾患であり、特有の自家蛍光性リポ色素蓄積物質が細胞内に蓄積することを特徴とします。これらの蓄積物は、超微細構造学的に異なるパターンで現れ、NCLの異なる型によって特有の形態が観察されます。例えば、CLN1型では「粒状浸透圧沈着症(GROD)」パターンが、CLN2型では「曲線状」プロファイル、CLN3型では「指紋状」プロファイルが最も一般的です。また、CLN4型からCLN8型にかけては、これらのパターンが混在することが一般的です。
NCLは、進行性の痴呆、てんかん発作、視覚障害といった症状を特徴とし、ZemanとDykenによって1969年に「神経性セロイドリポフスチン症」と名付けられました。Goebelは1995年に、NCLを小児期における神経変性疾患の中で最も一般的なものの一つとして指摘し、Moleらによる2005年の包括的なレビューでは、NCLの臨床的および遺伝的側面が詳細に調査されました。
これらの疾患は多くの場合、遺伝子変異によって引き起こされ、変異が発生する特定の遺伝子によってNCLの型が決定されます。これらの変異は、細胞が自己の廃棄物を処理する能力に影響を及ぼし、特に神経細胞にダメージを与えます。結果として、患者は一連の神経系の障害を経験し、これらの症状は徐々に進行します。NCLの研究と理解は、これらの症状を緩和し、将来的には治療法を開発するために重要です。
CLN1疾患の主な特徴と症状:
初期の発症: 通常、生後18ヵ月までに敏感さが増し、発達退行が始まり、以前に獲得した能力を失い始めます。
脳萎縮: 神経細胞が徐々に死滅し、脳組織が失われます。これにより、頭部が異常に小さくなる(小頭症)ことがあります。
運動機能の障害: 筋緊張の低下、知的障害、運動障害がみられ、罹患児は話したり歩いたりする能力を失う場合があります。
ミオクローヌスとてんかん: 2歳頃になると、筋肉の痙攣(ミオクローヌス)、てんかん発作、視力低下が現れるようになります。
呼吸器感染症: 頻繁に呼吸器感染症を起こすことがあります。
経管栄養の必要性: 病状の悪化に伴い、重度の摂食障害が発生し、経管栄養が必要になることがあります。
成人におけるCLN1疾患:
CLN1疾患は、小児期後半または成人期に症状が現れる場合もあり、これらのケースでは知的機能の低下、ミオクローヌス、てんかん、視力低下が特徴です。成人患者では、筋肉の協調運動障害(運動失調)やパーキンソニズムとして知られる運動異常が見られることもあります。
CLN1疾患は、特定の遺伝的変異によって引き起こされ、脳内に特定のタイプのリポフスチンと呼ばれる物質が蓄積することが特徴です。これらの蓄積物は神経細胞の機能を阻害し、最終的に細胞の死を引き起こします。
この疾患は、早期発見と対症療法による管理が重要ですが、現在、根本的な治療法は存在しません。研究と臨床試験が進行中であり、将来的には治療オプションが改善されることが期待されます。CLN1疾患は、その早期発症と進行性の性質により、患者とその家族にとって大きな挑戦をもたらします。
CLN1病、またはインファンタイル型神経セロイドリポフスチン症(NCL1)、はPPT1遺伝子の65以上の変異によって引き起こされる遺伝性障害で、精神および運動機能の発達障害、歩行・会話・知的機能の障害、再発性のてんかん発作、および視力低下を特徴とします。この疾患の徴候や症状は通常生後18ヵ月までに現れますが、個体差により成人期まで現れないこともあります。
PPT1遺伝子の変異は、パルミトイル蛋白チオエステラーゼ1酵素の産生や機能を低下させるか、または完全に消失させることによってCLN1病を引き起こします。最も一般的な変異の一つであるArg151Ter(R151X)は、酵素が早期に終了するため機能しなくなる異常に短い酵素を生じます。別の重要な変異であるArg122Trp(R122W)は、フィンランド系の人々においてこの疾患の多くの症例を引き起こします。
これらの変異による酵素の不足は、リソソームにおける特定のタンパク質からの長鎖脂肪酸の除去障害と、これらの部分的に分解された脂肪やタンパク質の蓄積を引き起こします。この蓄積は特に神経細胞に影響を及ぼし、早期に広範囲の神経細胞の損失を引き起こします。これがCLN1病における重篤な神経学的徴候や症状の原因となり、最終的には死に至ることがあります。
後期発症型CLN1病では、変異により正常レベルの機能が低下した酵素が産生され、徴候や症状の発現が人生の後半まで遅れることがあります。これらの症例では、リソソーム内への蓄積が徐々に進行し、神経細胞死が遅れるため、疾患の進行がより緩やかになります。
- セロイドリポフスチンとは?
-
セロイドリポフスチン (Ceroid lipofuscin) は、細胞内に蓄積する顆粒状の物質で、脂質とタンパク質の複合体です。この物質は、特に長期間にわたって細胞内に蓄積し、加齢や特定の遺伝性疾患、特にリソソーム(ライソソーム)蓄積症に関連しています。セロイドリポフスチンの蓄積は、細胞の機能障害や細胞死を引き起こし、組織の損傷や病態の進行に寄与することがあります。
特に、セロイドリポフスチンの蓄積は、神経セロイドリポフスチン症 (NCL;Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) と呼ばれる一群の進行性神経変性疾患において顕著です。これらの疾患は、バッテン病とも呼ばれ、視覚障害、精神運動機能の低下、認知機能の低下、てんかんなどの症状を引き起こします。NCLは遺伝的に異なる複数の形態があり、それぞれが特定の遺伝子の変異によって引き起こされます。
セロイドリポフスチンの蓄積は、その化学的性質と複合的な成分のため、研究が難しく、これまで完全には解明されていません。この蓄積物は、細胞の老化や病態のバイオマーカーとして使用されることがあり、特定の疾患の診断や治療の標的となる可能性があります。
遺伝的不均一性
CLN1(256730): 染色体1p32上のPPT1遺伝子(600722)の変異に起因します。CLN1病は、通常乳児期に発症し、発達の遅れ、筋緊張の低下、視力障害、てんかん発作などの症状を示します。
CLN2(204500): 染色体11p15上のTPP1遺伝子(607998)の変異によるもので、この型のNCLは特定の酵素不足により特徴づけられます。
CLN3(204200): 16p12上のCLN3遺伝子(607042)の変異が原因。このサブタイプは、特に視力障害や認知機能の低下を引き起こします。
CLN4(162350): 20q13上のDNAJC5遺伝子(611203)の変異による。成人期に発症することが特徴です。
CLN5(256731): 13q22上のCLN5遺伝子(608102)の変異によるもの。症状の発症時期と進行速度はこのサブタイプによって変わります。
CLN6: CLN6A(601780)とCLN6B(204300)は15q21上のCLN6遺伝子(606725)の変異による。異なる臨床的特徴を示します。
CLN7(610951): 4q28上のMFSD8遺伝子(611124)の変異による。視覚障害や運動機能障害を伴います。
CLN8: 北方てんかん変異型(610003)を含む、8p23にあるCLN8遺伝子(607837)の変異が原因。
CLN9 (609055): 分子生物学的にはまだ特徴づけられていません。
CLN10(610127): CTSD遺伝子(116840)の変異によるもので、カテプシンDの不足が関連しています。
CLN11(614706): 17q21上のGRN遺伝子(138945)の変異による。
CLN12/Kufor-Rakeb症候群(KRS;606693): ATP13A2遺伝子(610513)の変異による。以前はCLN12と呼ばれていましたが、現在ではKRSの変異型と考えられています。
CLN13(615362): 11q13上のCTSF遺伝子(603539)の変異に起因。
CLN14(611726): 7q11上のKCTD7遺伝子(611725)の変異による。
これらのサブタイプは、それぞれが特有の臨床的特徴を持ち、遺伝子変異によって引き起こされるNCLの多様性を示しています。治療は主に症状の管理に焦点を当てた支持療法が中心ですが、遺伝的診断により特定のサブタイプに対するより適切な管理とサポートが可能になります。
臨床的特徴
古典的乳児期発症CLN1
古典的乳児期発症CLN1(神経細胞性セロイドリポフスチン症1型)は、1968年にHagbergらによって初めて報告された「進行性脳症」として認識されました。この疾患は、精神発達障害、言語障害、小運動発作、運動発達の退行、運動失調といった特徴を持ち、血縁関係のないフィンランド人の両親を持つ小児に見られました。組織学的な所見では、脳皮質の細胞構造の完全な異常、白質の重度の変性、粒状物質の沈着が確認され、これは遊離脂肪酸と不飽和脂肪酸の存在を示唆しました。さらに、リノール酸代謝の障害が生化学的研究によって示されました。
SantavuoriらとHaltiaらは1973年に、乳児期発症CLN1の特徴的な臨床的および形態学的特徴をさらに詳細に明らかにしました。特に、大脳皮質の食細胞、異常に肥大した線維性アストロサイトの蓄積と重度の神経細胞破壊、血清レシチンの脂肪酸パターンの変化が報告されました。
Santavuoriらは1974年に、フィンランドの集団における乳児期発症CLN1が臨床的に均質であると報告し、生後6ヵ月から24ヵ月の間に現れる視覚障害、言語障害、運動障害、てんかん発作などの症状について詳述しました。これらの患者の多くは、3歳までに脳波で証明できる皮質活動が見られなくなりました。
Baumann and Markesberyは1982年に「サンタヴオリ病」として知られるこの状態について60例ほどが報告されていると述べ、アメリカでの初の症例を報告しました。彼らの研究は、特に循環白血球中に特徴的な封入体の発見を含みました。
Vanhanenらは1995年に、乳児神経性セロイドリポフスチン症患者の脳MRI所見を検討し、早期に検出可能な異常とその進行とともに変化する特徴を報告しました。
後期発症例では、Beckerらは1979年に若年期に発症したドイツ人の近親カップルの子供について報告し、その症状と化学的変化が乳児型のものと一致していたことを示しました。PhilippartらとHofman and Taschnerは若年発症型CLNの変種を報告し、特定の電子顕微鏡検査所見と症状の遅れた発現を示しました。
これらの報告は、CLN1病がいかに多様な臨床的表現を示すか、そしてその影響が神経系にどれほど深刻であるかを示しています。乳児期発症型では、病気の進行が早く、重篤な神経系の徴候や症状が早期に現れる一方で、後期発症型では症状の出現が遅れ、異なる臨床的特徴を示します。これらの知見は、CLN1病の診断と治療において重要な意味を持ちます。
成人発症CLN1
成人発症型ニューロナルセロイドリポフスチン症(CLN1病)のこれらの報告は、特にPPT1(パルミトイルタンパク質チオエステラーゼ1)遺伝子の変異に焦点を当てています。PPT1遺伝子はリソソーム酵素の一つであり、細胞の正常な機能維持に不可欠な脂質の代謝に関与しています。PPT1遺伝子の変異による酵素活性の低下は、セロイドリポフスチンと呼ばれる脂質含有顆粒の蓄積を引き起こし、神経細胞の死につながります。
Van Diggelenらによる2001年の研究では、成人発症型CLN1の例として、30代で発症し、進行性のうつ症状、認知機能の低下、小脳失調、パーキンソニズム、言語流暢性の低下を示した2人の姉妹が報告されています。これらの患者は、脳MRIで脳全体の萎縮を示し、酵素分析ではPPT1の重度の欠損が認められました。
Ramadanらの2007年の報告では、24歳で精神症状を示し、その後18ヶ月で症状が進行し、視野狭窄、網膜色素変性症、幻覚、さらには認知機能の低下が認められた女性が紹介されています。この患者も脳MRIで著明な大脳と小脳の萎縮が認められ、生化学的検査ではPPT1活性の低下が示されました。遺伝子解析により、PPT1遺伝子の2つの変異の複合ヘテロ接合が同定されました。
これらの研究は、成人発症型CLN1病が進行性の神経退行性疾患であり、精神症状、運動障害、視覚障害、そして最終的には認知機能の低下を特徴とすることを示しています。また、遺伝的解析がこの疾患の診断において重要であり、特定のPPT1遺伝子変異の同定が治療戦略の開発に役立つ可能性があることを強調しています。
マッピング
Jokiahoらの研究 (1990): フィンランドの乳児期発症CLN1家系を対象にした連鎖解析を通じて、バッテン病遺伝子(CLN3)が以前にマッピングされた16番染色体との連鎖がないことを示しました。これにより、CLN1型バッテン病の遺伝子が他の染色体上に存在する可能性が示唆されました。
Jarvelaらの研究 (1991): 小児期発症CLN1を持つフィンランド人15家族を対象にした研究で、1p染色体上へのCLN1遺伝子の連鎖が証明されました。Lodスコア(連鎖の統計的強度を示す値)が、特定のマーカーで3.38から3.56の間であったことから、この位置がCLN1遺伝子の存在場所である可能性が高いことが示されました。また、CLN1患者の曽祖父母の出生地を基にした分析から、非常に古い創始者効果の可能性が示唆され、CLN1遺伝子が染色体1p32にマッピングされました。
Hellstenらの研究 (1993および1995): CLN1と新たに発見された高多型マーカーとの間の連鎖不平衡を観察し、多点連鎖解析を強化することでCLN1遺伝子座のより精緻な割り当てが可能になりました。さらに、1995年の研究では、1番染色体1p32におけるCLN1遺伝子の正確な位置を特定するために、4 Mbのパルスフィールド・ゲル電気泳動(PFGE)地図を作成しました。この地図を用いて、CLN1遺伝子がMYCL1、RLF、COL9A2と密接に関連する1MBのコンティグ内に位置することが明らかにされました。
これらの研究成果は、バッテン病の遺伝学的基盤の理解を深める上で重要な進展を示しています。特に、CLN1遺伝子の正確な位置の特定は、疾患の診断、治療、および理解に向けた重要なステップです。
遺伝
常染色体劣性遺伝は、特定の遺伝病を引き起こす遺伝子の変異が両方の染色体上に存在する場合に疾患が現れる遺伝のパターンです。このタイプの遺伝においては、両親はそれぞれ変異遺伝子の1つのコピーを持っていますが、彼らは通常、症状を示しません。これは、彼らが疾患を引き起こす遺伝子の変異の「保因者」であるためです。
この遺伝のパターンにおいて、両親から変異遺伝子のコピーを1つずつ受け継ぐ子どもは、その疾患を発症します。つまり、子どもは両方の染色体上に変異遺伝子のコピーを持っているため、症状を示すというわけです。一方で、変異遺伝子の1つのコピーのみを受け継ぐ子ども(つまり、両親のうちの1人からのみ受け継ぐ)は、疾患の保因者になりますが、通常は症状を示しません。
常染色体劣性遺伝病のリスクを理解するためには、遺伝カウンセリングが有用であり、家族計画や将来の健康管理に関する意思決定を支援することができます。
頻度
特にフィンランドでは、CLN1疾患を含むNCLの発症率が高く、約12,500人に1人が罹患しています。これはフィンランド人口における特定の遺伝子変異の創設者効果や集団内結婚など、遺伝的要因が地域集団における疾患の高い発症率に影響を与えている可能性があることを示唆しています。フィンランドにおける高い発症率は、この国での遺伝的カウンセリングや疾患の早期診断、および治療戦略の開発において特に重要な情報となります。
CLN1疾患は、進行性の神経退行を引き起こし、重篤な物理的および精神的な障害を患者にもたらします。症状には、視覚障害、運動機能の低下、知的能力の低下、てんかん発作などが含まれます。早期発見と適切な支援が、患者およびその家族の生活の質を向上させる上で重要となります。
原因
CLN1病で見られるPPT1遺伝子の変異は、この酵素の正常な産生や機能を阻害します。酵素活動の低下または喪失は、リソソーム内での脂肪酸の除去過程を妨げ、結果として部分的に分解された脂肪やタンパク質が蓄積します。これらの蓄積物は、特に神経細胞で損傷を引き起こしやすく、CLN1病ではこれが早期に神経細胞の広範囲にわたる喪失を招きます。このため、小児期に重篤な神経系の徴候や症状が現れ、疾患が進行して死に至ることが多いです。
一方、CLN1病の後期発症型では、PPT1遺伝子の変異が酵素の部分的な機能を残す形で影響を及ぼします。これにより、酵素は幼児期早期に発症する患者に比べてある程度の機能を保ち、長鎖脂肪酸の除去やタンパク質の分解が部分的には行われます。しかし、これでもリソソームには未分解の物質が蓄積し、神経細胞死を引き起こしますが、そのプロセスはより緩やかであるため、症状の発現が人生の後半期にずれ込むことがあります。
このように、CLN1病はPPT1遺伝子の変異の種類や程度によって、発症時期や症状の重さに大きなバリエーションがあります。現時点では、この疾患の治療法は限られており、主に症状の管理と患者および家族へのサポートに焦点を当てたケアが提供されます。将来的には、遺伝子療法や酵素代替療法など、この遺伝子変異に対処するより効果的な治療方法の開発が期待されています。
診断
Voznyiらによる1999年の研究は、若年性バッテン病(CLN1病)の診断法の進歩を示しています。この研究で報告された新しい蛍光測定法は、4-メチルウンベリフェロンという蛍光色素を使用して、PPT1(パルミトイルタンパク質チオエステラーゼ1)の活性を測定します。PPT1は、若年性バッテン病の原因となる遺伝子にコードされた酵素であり、この病気の患者ではその活性が欠如しています。
この方法は、線維芽細胞、白血球、リンパ芽細胞、羊水細胞、および絨毛など、様々な組織や細胞タイプでPPT1活性を検出することができるという利点があります。特に、CLN1患者の組織ではPPT1活性が検出されないため、この測定法は若年性バッテン病の迅速かつ正確な診断を可能にします。このような診断ツールは、疾患の早期発見と適切な治療計画の確立に不可欠です。
この蛍光測定法は、従来の方法に比べて感度が高く、より少ない量のサンプルで検査を行うことができるため、診断過程を簡素化し、より効率的にすることが期待されます。また、この方法は非侵襲的なサンプル採取からもPPT1活性を検出可能であるため、患者にとっての負担が少なく、広範囲の臨床設定での利用が可能です。
この研究は、若年性バッテン病の診断における重要な進歩を表しており、疾患の早期発見と治療へのアプローチにおいて大きな可能性を秘めています。
病因
研究での主要な発見は、コントロールの脳サンプルと比較して、CLN1患者の脳組織でミトコンドリア・スーパーオキシドジスムターゼ-2(SOD2)、カスパーゼ-9(CASP9)、カスパーゼ-3(CASP3)、切断されたPARP1(Poly (ADP-ribose) polymerase 1)のレベルが上昇していたことです。これらの所見はアポトーシスによる急速な神経細胞死と一致しています。
Ppt1遺伝子欠損マウスの研究では、これらの発見が裏付けられ、培養された神経球の研究では、内腔(ER)ストレスが活性酸素種(ROS)レベルの上昇を引き起こし、これがさらに神経変性のプロセスを加速させる可能性が示されました。Kimらは、ヒトINCLにおける神経変性の急速な進行は、ERストレスを介したカスパーゼ-12(CASP12)の活性化、SOD2の産生の増加、および活性酸素産生の上昇によるカルシウム恒常性の不安定化によって引き起こされる可能性が高いと提唱しました。これらの異常は共に、CASP9、CASP3の活性化と、アポトーシスを示すPARPの切断を媒介します。
この研究は、CLN1病の病態生理におけるアポトーシスの役割と、特に小胞体ストレス応答と活性酸素種の増加がどのようにして神経細胞死を促進するかについての理解を深めるものです。この知見は、将来的な治療戦略の開発において、特にアポトーシス経路の抑制やERストレス応答の調節をターゲットとするアプローチの重要性を示唆しています。
分子遺伝学
Vesaらによる1995年の研究では、フィンランド人42家族のうち40家族の乳児期発症CLN1患者から、PPT1遺伝子のホモ接合体変異(R122W; 600722.0001)が同定されました。この結果は、フィンランド人口における創始者効果を示唆しています。
Mitchisonらは1998年に、若年発症CLN1患者11人におけるPPT1遺伝子の変異(600722.0002-600722.0006)を同定し、これらの変異が顆粒状浸透圧沈着症の超微細構造所見と関連していることを示しました。
Dasらによる1998年の研究では、29の患者由来細胞株から得られた58の変異対立遺伝子のうち57でPPT1遺伝子の19の異なる変異が同定されました。中でもR151X変異(600722.0006)が対立遺伝子の40%に、T75P変異(600722.0002)が13%に見られました。この研究では、患者の発症年齢が広範にわたり、50%が乳児期発症、17%が乳児期後期発症、33%が若年期発症であることが明らかにされました。
これらの研究結果は、CLN1病が遺伝的に非常に異質であることを示しており、患者の臨床的特徴や発症年齢に大きなばらつきがあることを示しています。PPT1遺伝子の変異に基づく詳細な分子遺伝学的分析は、CLN1病の診断、治療戦略の開発、および患者およびその家族への遺伝カウンセリングにおいて重要な役割を果たします。
集団遺伝学
Millerらによる2015年の要約によると、フィンランド人の中でのCLN1病の発症率は20,000分の1であり、保因者頻度は70人に1人と報告されています。この高い頻度は、「創始者効果」や遺伝的ドリフトなど、遺伝学的現象によって説明されることがあります。創始者効果は、比較的小さな先駆者集団からの人口が成長し、特定の遺伝子変異がその集団内で高頻度で継承される場合に発生します。フィンランドのように、比較的孤立した地理的または文化的集団では、この効果が顕著になることがあります。
CLN1病の保因者頻度が高いことは、フィンランド人口におけるこの遺伝子変異の広範な拡散を示しています。この情報は、特にフィンランドやその他の影響を受ける集団において、遺伝カウンセリングや疾患の予防戦略に重要な意味を持ちます。たとえば、この集団における出生前のスクリーニングや新生児スクリーニングプログラムの設計において、CLN1病のリスクを特に考慮に入れることができます。
動物モデル
Guptaら(2001): Ppt1およびPpt2遺伝子のノックアウトマウスモデルを作製し、これらのマウスが神経学的障害を発症することを示しました。Ppt1ノックアウトマウスは、運動異常が進行し、10ヶ月齢までに死亡しました。一方、Ppt2ノックアウトマウスはより長生きしましたが、両系統とも神経細胞の喪失とアポトーシスを示しました。
Zhangら(2006): PPT1欠損マウスが示す神経学的運動障害と進行性の神経細胞アポトーシスは、脳内の自家蛍光物質の蓄積とERの異常に関連していました。これは、パルミトイル化タンパク質の異常蓄積と未完成タンパク質応答の活性化によるものであると結論づけられました。
Kimら(2008): Ppt1欠損によるシナプス小胞関連タンパク質の異常な膜保持が、シナプス小胞のリサイクルの阻害につながり、神経伝達の障害を引き起こす可能性があることを示しました。
Millerら(2015): R151X PPT1変異をホモ接合体に持つトランスジェニックマウスモデルを作製し、ヒトのNCLの特徴を再現しました。また、リードスルー化合物であるアタルレン(PTC124)の投与が、変異マウスのPPT1酵素活性と蛋白レベルを増加させることを示し、治療の可能性を示唆しました。
これらの動物モデルを通じて、NCLの病態生理の理解が深まり、将来の治療法の開発に向けた重要な洞察が提供されています。特に、タンパク質の異常蓄積に関連する神経変性のメカニズムや、治療介入の可能性が明らかになりました。
命名法
しかし、遺伝子変異の同定と分子生物学的な理解の進歩により、この命名法は変化しました。現在では、NCLの分類は発症年齢ではなく、疾患の原因となる遺伝子の欠陥に基づいて行われています。この新しい分類法により、同じ遺伝子変異を持つものの、発症年齢や症状の重さが異なる場合でも、それらが同じ疾患群に属することが認識されるようになりました。
例えば、CLN1疾患は、発症年齢にかかわらず、PPT1遺伝子の変異によって引き起こされるNCLを指します。このような分類法により、疾患の遺伝的基盤に焦点を当てることで、研究者や臨床医が疾患メカニズムをより深く理解し、患者に対するより適切な治療戦略を立てることが可能になります。この分子異常に基づく分類法は、NCLの診断、治療、および研究において重要な役割を果たしています。
歴史
OppenheimerとAndrews(1959): 彼らは「セロイド貯蔵病」という用語を使用して、特定の患者群における病理学的所見を報告しました。彼らの報告したケースは、特に肝臓、脾臓、腸粘膜にセロイド(疾患特有の物質)の沈着が見られるという特徴がありました。これらの初期の報告は、セロイドリポフスチン症に対する関心を高め、その後の研究への道を開きました。
Nelsonら(1961): Nelsonらは、OppenheimerとAndrewsの報告に類似した臨床症状を持つ家族を報告しました。この家族研究は、疾患が遺伝的要因によって引き起こされる可能性があることを示唆しています。
Jonas(1966): Jonasによる孤発例の報告も、この疾患の理解を深めるのに貢献しました。これらの報告は、セロイドリポフスチン症が一つの病態ではなく、複数の関連病態を含む可能性があることを示唆しています。
Ryanら(1970): 「リポフスチン蓄積症」という用語を使用して、詳細な少年のケースを報告しました。彼らの報告は、疾患の病理学的側面に光を当て、後の分類と診断に貢献しました。
メンケス(1982): Ryanらの報告に基づいて、メンケスは電子顕微鏡検査の結果が満足できるものではなかったものの、臨床的根拠からこの病態がフィンランド型またはサンタヴオリ型の小児神経性セロイドリポフスチン症であると示唆しました。メンケスの見解は、この疾患群の分類と理解に重要な貢献をしました。
これらの報告は、セロイドリポフスチン症、特に若年性バッテン病の病態生理、遺伝学、および分類に関する早期の理解の基礎を築きました。後の年代において、遺伝子診断技術の進歩とともに、これらの疾患の分子生物学的基盤が明らかになり、より正確な診断と潜在的な治療法の開発につながっています。
疾患の別名
Infantile Batten disease
Infantile neuronal ceroid lipofuscinosis
Neuronal ceroid lipofuscinosis 1
Neuronal ceroid lipofuscinosis, infantile
Santavuori-Haltia disease
小児バッテン病
小児神経性セロイドリポフスチン症
神経細胞性セロイドリポフスチン症1
小児神経性セロイドリポフスチン症
サンタヴオリ・ハルティア病