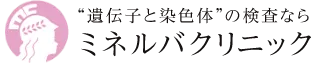疾患に関係する遺伝子/染色体領域
疾患概要
常染色体優性遺伝の下肢優位型脊髄性筋萎縮症-1(SMALED1)が、14q32染色体上のDYNC1H1遺伝子(600112)におけるヘテロ接合性変異によって引き起こされるため、番号記号(#)が使用されています。
脊髄性筋萎縮症(SMA)は、脊髄の運動ニューロンの変性により筋力低下が生じる遺伝性の神経筋疾患です。SMALEDは常染色体優性遺伝を示し、筋力低下は主に近位の下肢に影響を与えます(Harms et al., 2010)。
最も一般的な脊髄性筋萎縮症(例:SMA1、253300を参照)は、常染色体劣性遺伝を示し、5q染色体上のSMN1遺伝子(600354)の変異が原因です。
SMALED1はこのように、遺伝形式や影響を受ける部位が異なるため、特徴的な病態を示すことがわかります。
遺伝的不均一性
SMALED2A(615290)およびSMALED2B(618291)は、どちらも9q22染色体上のBICD2遺伝子(609797)の変異によって引き起こされます。これらの病型には以下の違いがあります:
– SMALED2A: 比較的軽度で、発症年齢が遅いことが多い。
– SMALED2B: より重症で、早期に発症し、より深刻な筋力低下を伴います。
これらのタイプは、下肢優位型脊髄性筋萎縮症における発症年齢と重症度の違いによって区別されます。
臨床的特徴
Young(1972年)は、この家族の追跡調査を行い、4世代にわたる13人の患者が常染色体優性遺伝の小児期発症脊髄性筋萎縮症(SMA)に一致する症状を示していることを報告しました。
SaulとMeyer(1985年)は、3世代にわたる5人の患者がいる家族について記述しました。
Harmsら(2010年)は、早期発症の脊髄性筋萎縮症で下肢に主に影響を与える、6世代にわたる大家族を報告しました。この家族では、大腿四頭筋の筋力低下が顕著で、股関節外転筋の萎縮も中等度から重度に見られました。発症は通常、生後2年以内でしたが、3人は4~7歳で発症しました。症状は進行せず、軽度の進行に留まり、患者は60歳代まで歩行能力を保っていました。筋電図検査や筋生検では、慢性脱神経が認められました。
Harmsら(2012年)は、遺伝子解析により確認されたSMALED患者の3世代にわたる家族について報告しました。患者は幼少期から不安定な歩行を示し、下肢の筋力低下が続きましたが、上肢には影響がなく、症状はほとんど進行しませんでした。膝の伸展筋力は著しく低下していました。筋電図検査では、慢性脱神経が示され、患者の一部には踵骨筋拘縮や内反足が見られました。
鶴崎ら(2012年)は、常染色体優性遺伝の脊髄性筋萎縮症で下肢優位の日本人女性とその2人の子供について報告しました。子供たちは歩行が遅れ、近位の下肢の筋力低下による不安定な歩行が続きました。筋生検では2型線維の著しい分節性萎縮が見られ、母親も軽度の筋萎縮がありました。
マッピング
LODスコア(logarithm of the odds)は、遺伝学において、ある遺伝形質が特定の遺伝子領域と連鎖している可能性を統計的に評価するために使われる指標です。LODスコアは、次のような考えに基づいています。
LODスコアが高いほど、その遺伝形質と特定の遺伝子領域が連鎖している可能性が高いことを示します。
一般的に、LODスコアが3以上であれば、その領域と遺伝形質が連鎖していると強く示唆され、信頼性のある証拠とされています(遺伝形質が連鎖している可能性が1,000倍高い)。
LODスコアが負の値であれば、連鎖がない可能性が高いことを示します。
具体的に、LODスコア5.10は、その遺伝形質(この場合はSMALED)が14q32染色体上の特定の遺伝子領域と連鎖している可能性が非常に高いことを示します。数値的にいうと、その領域がSMALEDと連鎖している確率が、連鎖していない場合の確率よりもおよそ100,000倍高いということになります。
一般的に、LODスコアが -2 以下であれば、遺伝形質と特定の遺伝子領域の間に連鎖がないと結論づけることができます。このスコアは、連鎖していない可能性が100倍高いことを示します。
まとめると:
LODスコアが3以上 → 連鎖があると考えられる(関連性が強く示唆される)。
LODスコアが -2以下 → 連鎖がないと考えられる(関連性が否定される)。
LODスコアが -2から3の間 → 連鎖の有無に関する証拠が不十分であるため、さらなるデータが必要。
この範囲を基に、研究者は遺伝子と疾患の関連性について判断を行います。
つまり、このスコアは、その領域が疾患に関与している可能性が極めて高いことを統計的に示していると言えます。
rs2615453とrs10143250の間の多地点パラメトリック lod スコアが3.00であったことから、14q32との連鎖はさらに裏付けられました。ハプロタイプ解析により、73の既知または予測遺伝子を含む、6.1 Mbの疾患関連領域が特定されました。Harms ら (2010) は、この疾患に対して脊髄性筋萎縮症-下肢優性 (SMALED) という名称を提案しています。
遺伝
GarvieとWoolf(1966年)やMageeとDeJong(1960年)なども、常染色体優性遺伝のSMAについて報告しており、同様の疾患表現型が見られています。
Pearn(1978年)は、小児期発症の常染色体優性SMAが、小児期発症SMA全体の2%未満を占めると推定しています。
Hausmanowa-Petrusewiczら(1985年)は、小児期および青年期に発症する近位型脊髄性筋萎縮症が、多様な表現型を示し、一部の症例は新しい優性変異による可能性があることを指摘しました。
Rudnik-Schonebornら(1994年)は、小児期発症の常染色体優性SMAが存在する証拠を提示しています。彼らは次の3つの証拠を挙げました:
1. 分離分析により、常染色体劣性遺伝からの逸脱が確認されました。
2. 2世代にわたる3つの家系で、疾患が新生突然変異として親に発症したことが示されました。
3. 5qマーカーとの関連を示さない93のSMA家系のうち、5つの家系でこの疾患が確認されました。
これらの研究により、小児期発症の常染色体優性SMAが独自の遺伝的背景を持つ疾患であることが示唆されています。
分子遺伝学
患者の皮膚線維芽細胞における実験では、ATP非存在下では微小管への結合が正常であったものの、ATP存在下では微小管への結合が著しく減少しました。これにより、変異ダイニンがダイニン複合体の安定性を損なっていることが示唆されました。さらに、32人の追加の発端者を対象にDYNC1H1遺伝子の配列決定を行ったところ、2つの家族でヘテロ接合型DYNC1H1変異(600112.0005および600112.0006)が特定されました。この所見は、DYNC1H1変異を持つロアホモ接合型マウスで観察された結果と一致しています【Hafezparast et al., 2003; Ori-McKenney et al., 2010】。
また、鶴崎ら(2012年)は、日本人の感覚症状のない同胞2人において、DYNC1H1遺伝子のヘテロ接合性ミスセンス変異(H306R; 600112.0001)を発見しました。この変異は、エクソームシーケンシングにより発見され、症状が軽度であった母親から遺伝したものです。さらに、Weedon ら(2011年)は、常染色体優性軸索シャルコー・マリー・トゥース病2O型(CMT2O;614228)の家族においても同じ変異を発見しています。
歴史
また、Buttら(1939年)が行った剖検報告書では、この家族の障害が遠位型ミオパチー(ジストロフィア・ミオトニア(160900)として誤って診断された)であるとの誤診がありましたが、その報告書でも患者が生産的な生活を維持できることが指摘されていました。さらに、この家族には、白内障、ミオトニア、糖尿病、精神発達障害などの追加の特徴は見られませんでした。
ウィリアム・スチュワート・ヤングの息子もまた、筋障害患者のための機械的補助具について有益な説明を行っており、Young(1949年)でその詳細が述べられています。
疾患の別名
SPINAL MUSCULAR ATROPHY, CHILDHOOD, PROXIMAL, AUTOSOMAL DOMINANT
SPINAL MUSCULAR ATROPHY, JUVENILE, PROXIMAL, AUTOSOMAL DOMINANT
KUGELBERG-WELANDER SYNDROME, AUTOSOMAL DOMINANT