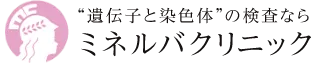疾患概要
ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ(DPD)欠損症は、個人によって症状の現れ方が異なり、神経障害の症状が顕著に見られる場合もあれば、全く症状がない場合もある疾患です。これは、症状の重症度に幅があることを特徴としています。
重度のジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ欠損症を持つ人では、症状が幼少期に現れることが多く、以下のような神経学的問題を抱えることがあります:
– てんかん発作の再発
– 知的障害
– 小頭症(頭囲が小さい)
– 筋緊張の亢進(筋肉が緊張しすぎる状態)
– 運動発達遅延(歩行や他の運動技能の発達が遅れる)
– 自閉症に似た行動(コミュニケーションや社会的相互作用に影響を与える)
一方で、無症候性(症状が現れない)患者も存在します。無症状の患者は、遺伝子検査や特定の検査を行わなければ診断されない場合もあります。
この疾患の重要な特徴の一つは、がん治療に使われるフルオロピリミジン系薬剤(例えば5-フルオロウラシルやカペシタビン)に対する重篤な毒性反応を引き起こすリスクがあることです。DPD欠損症では、これらの薬が体内で正常に分解されず、蓄積するため、以下のような生命を脅かす副作用が発生することがあります:
– 粘膜炎(口や胃腸管の粘膜に炎症や潰瘍が生じる)
– 口内炎、腹痛、出血、吐き気、嘔吐、下痢
– 好中球減少(白血球数の減少による感染リスクの増加)
– 血小板減少症(血小板の減少による出血リスクの増加)
– 手足症候群(手のひらや足の裏に発赤、腫れ、しびれ、皮膚剥離)
– 息切れ、脱毛
これらの副作用は、フルオロピリミジン系薬剤が体内で過剰に蓄積することによって引き起こされるため、DPD欠損症の患者では、薬剤の使用に際して特に注意が必要です。
ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ(DPD)欠損症の患者では、DPYD遺伝子における50以上の変異が確認されています。これらの遺伝子変異は、ウラシルやチミンといったピリミジン塩基の分解を妨げ、結果的にこれらの分子が血液、尿、脳脊髄液に過剰に蓄積します。ピリミジン代謝の障害が神経系に与える影響は十分には解明されていませんが、ウラシルとチミンの過剰蓄積が、ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ欠損症患者に見られる神経学的問題(知的障害、運動障害など)に関連している可能性が示唆されています。
さらに、DPYD遺伝子の変異は、5-フルオロウラシル(5-FU)やカペシタビンといった抗がん剤の分解にも影響を及ぼします。これらの薬は、ピリミジンに構造が類似しているため、DPD欠損症患者の体内で代謝されにくくなり、薬物が体内に蓄積してしまいます。その結果、薬物の過剰蓄積により、重篤な毒性反応や副作用(重篤な消化器症状、骨髄抑制など)を引き起こすことがあります。これが、ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ欠損症の患者が抗がん剤治療を受ける際に問題となる要因です。
臨床的特徴
ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ(DPD)欠損症
ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ(DPD)欠損症は、ウラシルとチミンというピリミジン塩基を分解する酵素であるDPDの欠乏によって引き起こされる遺伝性疾患です。これは常染色体劣性遺伝で遺伝することが知られており、発達遅滞、神経学的障害、てんかん発作などの多様な症状を引き起こします。
– Bergerら(1984年)は、3人の無関係な子供たち(男児2人、女児1人)に、ウラシル、チミン、5-ヒドロキシメチルウラシルの過剰な尿中排泄と脳機能障害が見られ、これがDPD欠損症を示唆することを報告しました。このうちの1人は、従兄弟同士の両親を持つことから、常染色体劣性遺伝が示唆されました。
– Wadmanら(1984年)は、自閉症の子供に見られたウラシルとチミンの異常な排泄パターンが、DPD欠損症によるものだと考えました。この研究は、神経発達の問題がピリミジン代謝の異常と関連している可能性を示しています。
– Brockstedtら(1990年)は、発達遅滞やてんかん、筋緊張亢進などの症状を呈した9人目の小児患者を報告しました。これまで報告された患者の多くがオランダ人であったことが注目されました。
– Van Gennipら(1994年)は、重度のDPD欠損症を持つオランダの患者を報告しました。この患者は、両側小眼球症、虹彩と脈絡膜のコロボーマ、眼振、進行性の精神運動発達遅延などの重篤な症状を示していました。
– Vrekenら(1997年)は、9ヶ月時点で熱性痙攣、重度の神経運動発達遅延、痙性四肢麻痺を示した子供の症例を報告しました。この患者では、6歳でチミン・ウラシル尿症が認められ、DPD欠損症が確認されました。遺伝子解析では、DPYD遺伝子にホモ接合性の終止変異が特定されました。また、この患者の先に生まれた兄弟も同様の症状で早期に死亡していたことが報告されました。
– Ennsら(2004年)は、パキスタン人の近親婚の両親から生まれた女児について報告しました。この女児は発育不全、発達遅延、低換気症、脳症、小頭症、眼振などの症状を示しており、脳MRI検査でも異常が確認されました。最終的には、てんかん発作や反復性の肺炎を発症し、生後31ヶ月で死亡しました。
これらの症例は、DPD欠損症が非常に多様な神経学的表現型を持つことを示しており、患者によって症状の重症度や発症年齢が異なることがわかります。また、DPYD遺伝子の変異がこの疾患の原因であり、特に近親婚が多い集団ではリスクが高いことも示唆されています。
5-フルオロウラシル毒性
5-フルオロウラシル(5-FU)は、主にがん治療に使用される抗がん剤で、ピリミジン代謝に関与する酵素であるジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ(DPD)が、この薬の代謝に重要な役割を果たします。DPDが欠損している場合、5-FUは体内で適切に分解されず、薬物が蓄積して重篤な毒性を引き起こすことがあります。以下は、5-FUの毒性に関連する症例や研究に関する概要です。
1. Tuchmanら(1985年)の報告では、27歳の女性が週1回の限定的な投与量で5-FUに異常に重篤な反応を示しました。口内炎、白血球減少症、脱毛、下痢、体重減少、小脳性運動失調などの神経症状が現れ、半昏睡状態にまで進行しました。この患者とその兄弟の尿にはウラシルとチミンが過剰に排出されており、ピリミジン代謝の異常が示唆されました。これにより、DPD欠損症が原因である可能性が示唆されました。
2. Diasioら(1988年)の症例では、乳がん治療のために5-FUを投与された40歳の女性が、重篤な神経毒性を発症しました。この患者の5-FUの消失半減期が著しく延長され、投与された薬物の約90%が未変化のまま尿中に排泄されました。この結果、DPD欠損が神経毒性の原因であることが示唆されました。
3. Sumiら(1996年)の報告では、無症候性のDPD欠損症の家族が研究され、発端者の姉が大量のジヒドロウラシルおよびジヒドロチミンを排泄していることが確認されました。この症例では、家族全員にDPD活性の異常が見られ、特にウラシルの代謝異常が強調されました。DPYD活性が低下している患者では、5-FU治療に対する重篤な副作用のリスクが高まることが示されました。
4. Milanoら(1999年)の調査では、5-FU関連の毒性に関連するDPD欠損症の53例が検討され、そのうち19例で中等度から重度のDPD欠損症が認められました。これらの患者は特に女性が多く(19例中15例)、DPD活性が低い患者では毒性スコアが有意に高いことが確認されました。主な症状として神経毒性が多く、まれに心毒性も認められました。
これらの報告は、5-FUの毒性がDPD欠損症と強く関連していることを示しており、DPYD活性が低下している場合、5-FUなどの薬物治療が慎重に管理される必要があることを示唆しています。
生化学的特徴
Bakkerenら(1984年)は、原因不明の痙攣を起こした小児患者で、尿中のウラシルおよびチミンの著しい増加を発見しました。この患者の尿中排泄物の定量結果では、正常値と比較して1000倍もの増加が見られ、血清および脳脊髄液中のピリミジン塩基レベルも正常値の約100倍に達していました。さらに、線維芽細胞でのジヒドロチミン脱水素酵素活性が完全に欠損していることが明らかになりました。この研究は、酵素欠損が証明された最初の症例であったことを強調しています。
Vrekenら(1997年)は、ほぼ完全なDPD酵素欠損を持つ患者の約50%が痙攣障害を示す一方で、急性5-フルオロウラシル(5-FU)毒性を示す患者では、通常DPD活性がヘテロ接合体の範囲内にあると述べています。このことは、5-FU治療に対する感受性が酵素活性の低下と関連している可能性を示しています。
Van Kuilenburgら(1999年)は、DPD欠損症に関連する臨床異常の根底には、ウラシル、チミン、およびベータ・アラニンの恒常性の変化がある可能性を示唆しました。特に、ベータ・アラニンは、中枢神経系で重要な抑制性神経伝達物質であるガンマ・アミノ酪酸(GABA)やグリシンの構造類似体であり、これが神経系の異常に寄与している可能性があると考えられています。
遺伝
Sumiら(1998年)は、ジヒドロピリミジン尿症が常染色体劣性遺伝であると結論づけ、ホモ接合型の患者は5-FUの毒性に対して非常に高いリスクを持つ可能性があることを示しました。しかし、ヘテロ接合型の患者では、リスクは比較的低い可能性があると指摘しています。これにより、DPDの欠損の程度が5-FU毒性に与える影響が明確に示され、治療において重要な遺伝的要因となることが明らかになりました。
頻度
分子遺伝学
また、Vrekenら(1997年)は、オランダの血族結婚による家族でDPD欠損症が発症した構成員について、DPYD遺伝子に4塩基対の欠失変異(612779.0003)を発見しました。
さらに、Van Kuilenburgら(1999年)は、完全型DPD欠損症の患者17家族22人を対象にした研究で、DPYD遺伝子に7種類の異なる変異を特定しました。中でも、最も一般的だった変異は、スプライス部位変異であるIVS14+1G-Aで、変異アレルの52%を占めました。しかし、この研究では、遺伝子型と表現型の相関関係は見られませんでした。
その後の研究で、Van Kuilenburgら(2009年)は、点突然変異が見つからなかった重度のDPD欠損症患者4名において、DPYD遺伝子内欠失を特定しました。3人の患者では、エクソン12の13.8kbがホモ接合性で欠失しており、1人はエクソン14から16にかけての122kbがホモ接合性で欠失していました。これらの患者はすべて近親婚の親から生まれました。また、5人目の患者では、4bp欠失(612779.0003)と、1p21.3-p13.3における14Mbの新生欠失が複合ヘテロ接合性として特定されました。この患者は、重度の精神運動発達遅延と特異な頭蓋顔面の特徴を示しており、これらの症状にこの遺伝子欠失が寄与している可能性が高いと考えられました。
総合的に、この研究において、DPD欠損症患者の7%にDPYD遺伝子に影響を与えるゲノム欠失が見つかり、特に広範囲の欠失は精神運動発達遅延やてんかん、低緊張、奇形などの重症型の症状を引き起こす可能性が示唆されました。
疾患の別名
Dihydropyrimidinuria
DPD deficiency
Familial pyrimidemia
Hereditary thymine-uraciluria