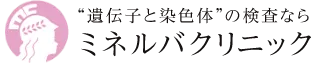疾患に関係する遺伝子/染色体領域
疾患概要
● ジストロフィン遺伝子と変異
両疾患の原因となるジストロフィン遺伝子は非常に大きな遺伝子で、約3分の2の患者で1つまたは複数のエクソンの欠失が認められています。DMD患者では、多くの場合、これらの欠失がフレームシフトを引き起こし、機能するジストロフィンが全く作られないことが、疾患の重症度につながります。一方、BMD患者では、フレームシフトが起こらず、部分的に機能するジストロフィンが作られるため、症状が軽くなることが多いです。
● 臨床的特徴
デュシャンヌ型筋ジストロフィーは、幼児期に診断され、4歳から5歳での発症が一般的です。進行は急速で、10歳前後で車椅子の使用が必要となり、心筋機能不全や平滑筋の機能障害が15歳から20歳の間に見られることが多くなります。Bolandら(1996年)の調査では、患者の平均寿命は17歳であり、心臓や消化管の合併症が主な死因として報告されています。
BMD患者では、発症年齢が遅く、筋力低下の進行も遅いため、歩行能力を長期間維持することが可能です。また、心筋症が発症することがありますが、DMDほど頻繁ではありません。
● 症状の相関
DMDとBMDの症状の重症度は、遺伝子変異の種類や位置に依存しますが、必ずしも欠失の大きさと病気の重症度が直接相関するわけではありません。
臨床的特徴
骨格筋
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)の骨格筋に見られる特徴は、進行性の近位筋のジストロフィーと、特にふくらはぎにおける偽性肥大です。偽性肥大とは、筋肉が見た目には肥大しているように見えても、実際には筋肉が線維化や脂肪浸潤に置き換わっている状態を指します。外眼筋は影響を受けないため、球麻痺(目の筋肉が麻痺する症状)は見られませんが、心筋はしばしば影響を受けます。
● 骨格筋の特徴
DMD患者では、以下の筋肉に関連する変化が観察されます:
– 血液中のクレアチンキナーゼ(CK)値の上昇:これは筋肉の損傷を示す主要な指標です。
– 筋電図(EMG)の異常:筋原繊維の異常が確認されます。
– 筋生検では、筋線維の変性、筋線維の代わりに起こる線維化、および脂肪浸潤が見られます。
DMDの進行は一般に3歳以前に始まり、12歳までに車椅子が必要になるケースがほとんどです。さらに進行すると、20歳までに呼吸不全や心不全で死亡する例が多いです。一方、ベッカー型筋ジストロフィー(BMD)はより進行が遅く、発症は20代から30代にかけて見られることが多く、より長生きすることが可能です。
● 他の影響
モザーとエメリ(1974年)は、女性ヘテロ接合体にも筋ジストロフィーに似たミオパチーが見られる場合があることを報告しており、特に血清CK値の上昇が顕著であることがわかっています。これに加え、DMD患者はカリウム欠乏に対する感受性が高く、低カリウム血症が死に至るリスクを高めることが指摘されています【Soloway & Mudge, 1979】。
● 骨格筋における分子レベルの変化
Frigeriら(1998)とWakayamaら(2002)の研究では、アクアポリン-4(AQP4)の発現がDMD患者の骨格筋で著しく減少していることが報告されています。AQP4は水分子の輸送に関与するタンパク質であり、その減少はDMDにおける膜の変化に関連していると考えられています。
野口氏ら(2003年)の研究では、DMD患者の筋組織における遺伝子発現を解析し、免疫応答や細胞外マトリクス、シグナル伝達に関連する遺伝子の発現が増加していることが確認されています。これらの変化は、筋組織の壊死、炎症、再生プロセスを反映しています。一方、筋のエネルギー代謝や恒常性に関わる遺伝子の発現は減少しており、筋肉のエネルギー供給能力が低下している可能性が示唆されています。
心筋
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)では、心筋も影響を受け、特に拡張型心筋症が特徴的です。DMD患者では、心筋症の兆候は6歳頃までに現れ始め、病気が進行するにつれてその割合は増加し、生涯の最終段階では95%に達します【Nigro et al., 1983】。DMDの進行による心筋障害は、筋肉の変性と類似しており、心筋の収縮・弛緩の繰り返しによる損傷が進行性に進みます。
一方で、ベッカー型筋ジストロフィー(BMD)では、21歳以前に重度の心筋症が発症することは稀です。また、13歳以前に心臓の異常が見られる患者はほとんどいません【Nigro et al., 1983】。
● DMDヘテロ接合体の女性キャリアにおける心筋症
女性キャリアでも心筋症が発症することがあります。Mirabellaら(1993年)の研究では、DMDヘテロ接合体の女性の6.6~16.4%に心電図異常が報告されており、筋力低下を伴う重度の心筋症が見られるケースもあります。彼らの報告では、2人のキャリア女性患者で拡張型心筋症と血清クレアチンキナーゼ(CK)値の上昇が確認されましたが、筋力低下の症状は見られませんでした。この2人の患者の心臓生検では、多くの心筋線維でジストロフィンが欠如していることが確認されました。これは、キャリア女性でもジストロフィン欠損により心筋が障害を受ける可能性があることを示唆しています。
● 心筋への影響のまとめ
DMDおよびBMDにおける心筋症の進行は、骨格筋の損傷と同様に、ジストロフィンの欠如に起因します。ジストロフィンは心筋細胞を安定させる役割を持っており、その欠如により、心筋細胞が徐々に損傷し、拡張型心筋症などの心疾患が引き起こされます。また、DMDのキャリアである女性でも心筋症が発症するリスクがあり、定期的な心臓検査が推奨されます。
平滑筋
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、骨格筋だけでなく平滑筋にも影響を与え、特に胃腸管の平滑筋に障害が現れることがあります。Barohnら(1988年)の研究では、DMD患者において、急性胃拡張や腸管偽閉塞などの平滑筋機能障害が発生することがあり、これが場合によっては致命的な結果をもたらすことが示されています。彼らは11人のDMD患者の胃排出機能を調査し、その結果、胃排出時間が著しく遅延していることが確認されました。この平滑筋障害により、消化管の動きが遅くなり、食物の消化と排出に影響が出ることがあるのです。
● 眼外筋が影響を受けない理由
興味深いことに、DMDの進行中に、眼外筋(EOM)は臨床的に影響を受けないままです【Kaminski et al., 1992】。これは他の筋肉とは対照的であり、この特徴的な現象の原因については、Khuranaら(1995年)が研究を行っています。彼らは、ジストロフィン欠損症が眼外筋において筋壊死や病的に上昇した細胞内カルシウムレベルを引き起こさないことを明らかにしました。また、in vitro実験では、眼外筋が他の横紋筋(例: 大胸筋)に比べて、上昇した細胞内カルシウムによる壊死に対して抵抗性を示すことが確認されています。
● カルシウムホメオスタシスの重要性
Khuranaらは、眼外筋がDMDの影響を受けにくいのは、カルシウムホメオスタシスを維持する能力が優れているためであると示唆しています。この発見は、DMDにおける筋障害の進行メカニズムを理解するうえで重要であり、細胞内カルシウムレベルを調節することが、DMDの潜在的な治療法として活用できる可能性が示唆されています。カルシウムの異常がDMDでの筋壊死の重要な要因であるため、この方向でのさらなる研究が治療に役立つかもしれません。
神経系
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、進行性の筋力低下だけでなく、神経系にも影響を及ぼすことが知られています。特に、DMD患者の一部では軽度の精神発達障害が見られ、これはジストロフィン遺伝子の多面的な影響によると考えられています【Zellweger & Niedermeyer, 1965】。
● ジストロフィンと脳の関係
脳におけるジストロフィンmRNAの発見により、DMD患者の精神発達障害とジストロフィン欠損との関連が示唆されています。ジストロフィンは筋肉だけでなく脳にも発現しており、このことが神経系への影響を通じて、DMD患者の知的障害に関連している可能性があります。Bresolinら(1994年)の研究では、DMD患者50人のうち31%が知能指数(IQ)75以下であることが報告され、適切なIQレベルに達していたのは24%に過ぎませんでした。
● 知的障害と遺伝子変異の関係
ジストロフィン遺伝子の突然変異の性質が、精神発達障害の発症に影響を与えるかどうかについても研究されています。Bushbyら(1995年)は、DMDの男児74人を対象に調査を行い、18%がIQ70以下の知的障害を持つことを報告しました。ただし、ジストロフィン遺伝子のプロモーター領域の欠失と知能指数(IQ)との間には有意な関連性が見られませんでした。さらに、遺伝子欠失の長さとIQの間にも明確な関連性は認められませんでしたが、遠位欠失を持つ男児の方が、近位欠失を持つ男児よりも精神発達障害が見られる傾向があることがわかりました。
● DMDの異質性
また、DMD患者の中には重度の精神障害を持つ患者と持たない患者が存在し、この異質性が注目されています。Emeryら(1979年)は、精神障害の重症度に基づいて患者を分類し、重度の精神障害を持つ患者は発症年齢が遅く、筋力低下が進行しやすいという傾向を示しています。
これらの知見は、DMDの神経系への影響が、単に筋肉におけるジストロフィン欠損にとどまらず、脳におけるジストロフィンの機能不全にも関連していることを示唆しており、ジストロフィン遺伝子変異の種類や位置が知的障害の発現に影響を与える可能性が示されています。
網膜機能
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)およびベッカー型筋ジストロフィー(BMD)の患者において、網膜神経伝達の異常が観察されています。これらの異常は、主に網膜電図(ERG)によって検出されており、光受容体や双極細胞に影響を与える異常が確認されています。
● 網膜機能とDMD/BMD
DMD患者では、暗順応ERGにおいて、a波は正常ながらb波が減少することが報告されています。これは、光受容体(a波)には問題がない一方で、ON双極細胞(b波)で異常が発生していることを示しています【Cibis et al., 1993; Pillers et al., 1993】。DMDの患者はb波の振幅が減少することが多いものの、夜盲症や視覚異常は報告されていません。
Jensenら(1995年)は、DMD/BMDの男児16人を調査し、10人で陰性ERGが見られたことを報告しています。この陰性ERGは、主に網膜またはグリア細胞におけるジストロフィンの欠損に関連していると推測されていますが、視覚機能そのものには異常は見られませんでした。
● 網膜におけるジストロフィンの役割
DMD患者における網膜のジストロフィンアイソフォーム、特にDp260は、網膜機能に重要な役割を果たしている可能性があります。これが欠損すると、視覚伝達の一部に影響を与えることが示唆されていますが、日常生活での視覚障害にはつながらないことが多いです【Costa et al., 2007】。
● 色覚異常
Costaら(2007年)による研究では、DMD患者44人を対象にした色覚検査で、赤緑色覚異常が47%(21/44)に認められました。この異常は特にエクソン30の下流で欠失がある患者で顕著であり、66%が赤緑色覚異常を示しました。エクソン30の上流に欠失がある患者では、色覚異常は認められませんでした。これにより、ジストロフィンDp260アイソフォームの欠如が、色覚異常と関連している可能性が示唆されました。
● ミュラー細胞とAQP4
ジストロフィン欠損症に関連する網膜機能異常に加えて、アクアポリン4(AQP4)という水チャネルの役割も重要視されています。Liら(2002年)は、AQP4ノックアウトマウスの研究により、AQP4が網膜のミュラー細胞において体液バランスを維持し、神経信号伝達を促進している可能性を示しました。AQP4の欠如により、網膜機能が軽度に損なわれることが明らかになりました。
● 結論
DMDおよびBMD患者の網膜機能には、ジストロフィン欠損により特定の視覚伝達経路に異常が見られることが確認されていますが、通常の視覚機能にはほとんど影響がないことが多いです。特に、色覚異常や網膜の微細な機能障害が一部の患者で見られるものの、日常生活に支障をきたすレベルではないことが多いです。
保因女性
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)およびベッカー型筋ジストロフィー(BMD)のキャリア女性は、これまで男性と比べて症状が軽いと考えられていましたが、近年の研究では、キャリア女性にもさまざまな症状が発現する可能性があることが明らかになっています。
● 心筋症とキャリア女性
Schade van Westrum 氏ら(2011年)の研究では、DMDまたはBMDの変異を持つ99人のオランダ人女性キャリアを9年間追跡したところ、10%(11人)が拡張型心筋症(DCM)を発症していることが確認されました。特に、追跡期間中に9人の女性が新たにDCMを発症しており、年齢が高くなるにつれてリスクが増加することが示されました。これらのキャリア女性は、高血圧や労作時の呼吸困難、胸痛といった症状を伴うことが多く、進行性の心臓異常を発症するリスクが高いことが分かっています。したがって、DMDやBMDのキャリア女性は定期的な心臓評価(心エコー検査など)を受けることが推奨されています。
● 筋力低下とキャリア女性
Mercier ら(2013年)の研究では、17歳以前に疾患関連の症状を示したDMD遺伝子の変異を持つ女性キャリア26人を対象に、その特徴が調査されました。この研究では、5人がDMDのような重度の筋力低下を示し、15歳以前に歩行不能となりました。13人はベッカー型のように軽度の筋力低下を示し、15歳以降も歩行可能でありましたが、運動耐性が低下していました。初期の症状としては、下肢の著しい筋力低下が88%に認められ、運動不耐性は27%に見られました。
● 認知機能とキャリア女性
また、認知障害が27%のキャリア女性に見られ、これは遺伝子の遠位部分の変異と関連があるとされました。キャリア女性においても、ジストロフィンの異常が脳に影響を与えることが示唆されています。
● 筋生検とX染色体不活性化
さらに、筋生検では、83%のキャリア女性にジストロフィー性変化が認められ、ジストロフィンに対するモザイクパターンの免疫染色が81%の女性で観察されました。また、62%のキャリア女性では、X染色体不活性化の偏りが見られ、これが症状の発現に影響している可能性があります。
● 結論
DMDやBMDのキャリア女性は、必ずしも無症状ではなく、心筋症や筋力低下、認知障害などの症状を発症するリスクがあります。これらのリスクは年齢とともに増加し、特に心臓や筋肉の機能障害が進行する可能性があるため、定期的な医療監視と早期の介入が重要です。
その他の特徴
● 筋芽細胞の機能異常
Blau ら(1983年)の研究では、DMD筋組織から得られる筋芽細胞の生存率や増殖能力が低下していることが報告されました。しかし、この仮説は後に否定され、DMD遺伝子の欠陥が筋芽細胞の増殖能力には直接影響しないことが示されています(Webster ら、1986年; Hurko ら、1987年)。
● 細胞膜の異常
Baricordi ら(1989年)の研究は、DMD患者のリンパ球におけるキャッピング現象の障害が細胞の内在的な欠陥であり、DMDにおける細胞膜全体の障害が進行している可能性を示唆しました。これにより、筋肉以外の細胞や組織にも影響を与えていることが示されています。
● 遺伝子発現と再生能力
Haslett ら(2002年)の研究では、DMD患者の筋肉で発現している遺伝子のプロファイルが、炎症や結合組織の過剰増殖、および再生の試みを反映していることが明らかになりました。DMD筋では、ジストロフィン遺伝子が発現不足である一方で、再生を促す遺伝子が過剰発現していることが特徴的です。
● 一酸化窒素合成酵素(NOS)の減少
筋膜に関連する神経型一酸化窒素合成酵素(NOS1)の発現がDMD患者で低下していることも確認されており、呼気中の一酸化窒素のレベルが低いことが、筋肉機能や血管機能に悪影響を与えていると考えられます(Straub ら、2002年)。
● ユトロフィンの増加
ユトロフィンは、ジストロフィンと機能的に類似しており、DMD患者の筋細胞膜での発現が年齢とともに増加することが確認されています。ユトロフィンの発現は、DMD患者において病気の進行や症状の改善に寄与している可能性があり、重症度の軽減に関連していると考えられています(Kleopa ら、2006年)。
● 手術中の出血リスク
DMD患者は、手術中の出血量が多いことが報告されています。Labarque ら(2008年)は、DMD患者の血小板におけるジストロフィンDp71およびDp116の発現低下が、血小板の凝集能力の低下と関連していることを示しました。これにより、血小板機能障害が手術中の出血量の増加につながる可能性があります。
これらの研究結果は、DMDが単に筋肉の病気ではなく、全身のさまざまな組織や細胞機能に影響を及ぼす多面的な疾患であることを示しています。
マッピング
Lindenbaumら(1979年)は、X-1転座を伴うDMDを発見し、DMD遺伝子がXp1106またはXp2107にあることを示唆しました。その後の研究でも、Xp21における転座や遺伝子欠失がDMD発症に関与することが確認され、転座によって正常なX染色体が不活性化され、DMDの症状が現れることが多いとされています。
Murrayら(1982年)は、DMD遺伝子と約10cM離れた位置にある制限酵素多型との連鎖を発見し、これがXp22.3-p21に位置することを明らかにしました。Wieackerら(1983年)やWortonら(1984年)は、DMD遺伝子の位置をさらに詳しく解析し、21番染色体上のリボソームRNAをコードする遺伝子ブロックとの連鎖や転座を持つ女性におけるDMD発症メカニズムを研究しました。
また、Franckeら(1985年)は、DMDと網膜色素変性症(RP)およびマクラウド赤血球表現型を伴う慢性肉芽腫性疾患を持つ男性患者を研究し、これらが連続遺伝子症候群として知られる疾患群に関連することを示唆しました。この患者では、Xp21に非常に微細な欠失があり、これが複数の遺伝子の異常を引き起こしている可能性が示されました。
Kingstonら(1983年、1984年)は、クローン化配列L1.28(DXS7)とベッカー型筋ジストロフィー(BMD)との連鎖を発見しましたが、DMD遺伝子とXg遺伝子との関連は認められず、DMDと色覚異常との関連も否定されました。
Grimmら(1989年)は、DMD遺伝子座内のDXS164に関連する組み換え率を報告し、組み換えのホットスポットが存在する可能性を示唆しました。このように、DMD遺伝子の細かな位置やその周辺遺伝子との連鎖に関する研究は、DMDの遺伝的背景の解明に大きく貢献しています。
これらの知見により、DMD遺伝子がX染色体上のXp21に位置し、遺伝子欠失や転座によって発症することが明確にされ、DMD発症メカニズムの理解が進みました。
遺伝
Caskeyら(1980)とBucherら(1980)は、DMDにおける新しい突然変異の割合が理論上の3分の1に近いことを報告しました。一方で、Bucherらの研究では、55人の母親のうち9人(16.4%)が非保因者であることが判明しました。この結果は、DMDにおける突然変異率が女性よりも男性で高い可能性を示唆しており、DMDの発症には男性側での突然変異が重要であることが示されています。
また、Barbujaniら(1990年)は、DMD患者の家族1,885世帯における調査から、散発的な症例の割合が0.229であると算出しました。これは、突然変異と自然選択の平衡に基づく予測値である0.333から有意に低い結果です。彼らは、これを説明する仮説の一つとして母親の生殖細胞におけるモザイク現象を提案しました。この現象では、母親の生殖細胞内で異なる遺伝情報が混在し、同一家族内で複数のDMD症例が発生する可能性が示唆されています。
さらに、Borresenら(1987年)の研究では、祖父の精子で突然変異が発生したことが確認され、性腺モザイクの可能性が示唆されました。このことは、DMDが突然変異によって発生する可能性があり、母親の他の親族が必ずしも保因者でないことを示唆しています。
DMDにおける突然変異は、特定の家族や集団において異なる発生率を持つことが確認されており、Vitielloら(1992年)は北東イタリアのDMDおよびBMD患者の調査で、筋プロモーター領域での突然変異の例を発見できなかったと報告しています。これらの研究は、DMD遺伝子がさまざまな形で突然変異する可能性があることを示し、その遺伝的背景が複雑であることを示しています。
全体として、DMDの発症には新しい突然変異が重要な要因であり、遺伝的モザイク現象や性別による突然変異率の差など、さまざまな要因が関与していることが示唆されています。
性腺モザイク
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)に関連する性腺モザイクは、複数のDMD患者を持つ家族において重要な遺伝的現象として認識されています。性腺モザイクとは、遺伝子変異が受精後に生じ、発端者の性腺(卵巣や精巣)内で異なる遺伝子セットが混在する現象です。この結果、親が変異を持っていなくても、複数の子供がDMDなどの遺伝性疾患を発症することがあります。
WoodとMcGillivray(1988)は、性腺モザイクの可能性が示唆される家族について説明しています。この家族では、DMD患者の母親が異なる3種類のX染色体を子供に伝達しており、著者らは、この患者の突然変異が受精後に生じたと推測しています。これにより、性腺内にモザイク状態が発生し、異なるX染色体が子供たちに伝えられた可能性があるとされています。
Witkowski(1992)は、生殖細胞モザイクの別の可能性として、**キメラ**の概念を提案しました。キメラとは、2つの異なる受精卵が融合し、一つの個体を形成する現象であり、この場合、女性は突然変異を持つ受精卵と正常な受精卵から形成される可能性があります。このため、生殖細胞モザイクと同様の遺伝的特徴を示すことがあると考えられます。
また、Melisら(1993)は、DMDを発症した兄弟2人を持つ家族を報告しており、筋ジストロフィンの免疫組織化学的分析とハプロタイプ分析により、DMD遺伝子が母方の祖父から孫たちに伝えられたことが確認されました。この研究では、2人の可能性のある保因者を特定することで、適切な遺伝カウンセリングが行われ、次世代におけるDMD患者の発生を防ぐことができました。
Passos-Buenoら(1992)の研究では、24例の生殖細胞モザイク症例が報告され、そのうち79%がDMD遺伝子の近位部分に突然変異を持ち、21%が遠位部分に突然変異を持つことが示されました。この結果は、生殖細胞モザイクがDMDにおいて重要な役割を果たしていることを示唆しています。
総じて、**性腺モザイク**は、DMDの遺伝パターンに影響を与え、家族内で複数の発症者が出る場合があることが明らかになっています。この現象は、遺伝カウンセリングにおいて考慮すべき重要な要素です。
体細胞モザイクとヘテロ接合型女性
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)の体細胞モザイクやヘテロ接合型女性に関する研究は、DMDの発症メカニズムの理解を深める重要な要素となっています。
1. 体細胞モザイクとDMD
体細胞モザイクとは、体細胞における遺伝子変異が部分的に発生し、その結果、異なる遺伝子構成を持つ細胞が同じ個体内に存在する現象です。DMD患者の筋組織には、まれにジストロフィン陽性の筋線維(リバータント線維)が見られることがあり、これは体細胞モザイクの存在を示唆しています。Kleinら(1992年)の研究では、欠失部分に対する抗体で染色されない筋線維が見つかり、これらの陽性線維は体細胞モザイクによるものではなく、むしろ二次的な欠失やスプライシング修正の結果である可能性が高いと結論づけられました。Thanhら(1995年)の研究も、ジストロフィンmRNAのフレームシフト修正が起こることで、一部の筋線維が正常なジストロフィンを産生することを示しています。これらのリバータント線維は、体細胞モザイクに加えて、スプライシングの変化や二次的な体細胞変異が関与している可能性があります。
2. ヘテロ接合型女性とX不活性化
DMDはX連鎖性遺伝疾患であり、通常は男性に発症しますが、女性のヘテロ接合体でも、X染色体のライオン化(X不活性化)によって症状が現れる場合があります。X不活性化は、女性の2本のX染色体のうち1本がランダムに不活性化される現象です。しかし、この不活性化が偏ることで、ヘテロ接合体である女性にもDMDが発症することがあります。Burnら(1986年)は、一卵性双生児の女児で、片方がDMDを発症し、もう片方が正常であった例を報告し、この違いはX不活性化の偏りによるものだとしました。さらに、Pegoraroら(1994年)は、DMDキャリア女性のX不活性化が偏っているケースが多いことを示し、特に父方由来のX染色体が不活性化される傾向があると指摘しました。
3. ヘテロ接合型女性の臨床的特徴
一部の女性キャリアは、DMDやベッカー型筋ジストロフィー(BMD)の症状を呈することがあります。Rajakulendranら(2010年)は、体側の筋萎縮が顕著なヘテロ接合型女性2例を報告し、これらの患者は筋萎縮や脂肪置換、クレアチンキナーゼ(CK)値の上昇などDMDの典型的な症状を示しました。X不活性化の偏りと体細胞モザイクが、この非対称性症状の発現に寄与している可能性が指摘されています。
4. 性腺モザイク
DMDにおける性腺モザイクは、発端者の親が保因者ではない場合でも、次世代に疾患を引き起こす可能性がある現象です。WoodとMcGillivray(1988年)は、DMD患者の女性先祖が異なるX染色体を複数の子供に伝えた事例を報告し、生殖細胞モザイクの存在を示唆しました。また、Passos-Buenoら(1992年)は、24例の性腺モザイク症例を分析し、そのうち79%が近位部分に突然変異を持つことを確認しました。
5. X不活性化に関連する遺伝的メカニズム
DMDの発症には、X不活性化の他にもさまざまな遺伝的メカニズムが関与していることがわかっています。たとえば、Chellyら(1986年)は、DMDとターナー症候群(45,XO)を併発した症例を報告し、X染色体の一部の欠失がDMDを引き起こすことを示しました。また、Katayamaら(2006年)は、アンドロゲン不応症候群(AIS)とDMDの両方を持つ女性を報告し、この症例ではAR遺伝子の変異とDMD遺伝子の独立した変異が関与していることを明らかにしました。
総じて、DMDに関連する体細胞モザイクやヘテロ接合体女性の発症メカニズムは、X不活性化の偏りや遺伝的モザイクの影響を受けており、さらなる研究が必要とされています。また、性腺モザイクは家族内におけるDMDの遺伝パターンに影響を与える重要な要素として注目されています。
頻度
原因
● DMD遺伝子の変異とその影響
DMD遺伝子に異常が発生すると、生成されるジストロフィンの構造や機能に影響が及びます。以下のように、変異の種類によって異なる筋ジストロフィーが引き起こされます:
– ベッカー型筋ジストロフィー(BMD):変異により、異常なジストロフィンが生成されますが、部分的に機能が保たれます。このため、筋力低下の進行は遅く、症状も軽い場合が多いです。
– デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD):変異によって、完全に機能を持つジストロフィンが生成されなくなり、筋力低下が早期に始まり、進行が速い重篤な病態を引き起こします。
● 筋細胞への影響
ジストロフィンが十分に存在しない場合、筋細胞は収縮や弛緩の過程で損傷を受けやすくなります。この損傷が繰り返されることで、筋線維は次第に弱体化し、最終的に死滅していきます。この結果、筋肉の萎縮や心臓障害が発生し、これらはDMDやBMDに共通して見られる特徴的な症状です。
● ジストロフィン症候群
ジストロフィンが欠損している、もしくは機能しないことが原因となるこれらの病態は、ジストロフィン症候群としてまとめて分類されます。
診断
症状のあるヘミ接合体
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、典型的な症状から比較的簡単に臨床診断が行われます。3歳頃に始まる歩行困難や腓腹筋の仮性肥大、進行性の筋力低下、そして血清中のクレアチンキナーゼ(CPK)値の大幅な上昇が見られます。これらの特徴により、DMDの診断が疑われ、さらに筋電図検査や筋生検によって確定診断が行われます。
初期段階では、筋生検の結果が炎症性変化と類似しているため、誤って多発性筋炎と診断される可能性もあります。そのため、慎重な組織学的観察が必要です。
● 生化学的診断と出生前診断
Heyckら(1966年)は、生後9日目の乳児においてCPK値の大幅な上昇を記録しました。しかし、Dubowitz(1976年)の研究では、臍帯血中でのCPK上昇は確認されていません。周産期における他の要因もCPK値の上昇に影響を与えるため、これらの検査だけではDMD診断には不十分です。
Mahoneyら(1977年)は、胎児の血液中CPKの上昇と中絶後の骨格筋の組織学的変化を利用して、DMDの出生前診断の有効性を示しましたが、完全な確実性が伴うわけではありませんでした。Bartlettら(1988年)は、欠失マッピングがより信頼性の高い出生前診断手法であることを提案しました。これにより、DMDの出生前診断や保因者検出がより精度の高いものとなります。
● 分子診断の進展
BeggsとKunkel(1990年)は、DMDの分子診断に関するフローチャートを提案しています。まず、ジストロフィンのウェスタンブロット検査を行い、欠損が確認されればDMD、減少していればベッカー型筋ジストロフィー(BMD)の可能性があります。さらに、PCRやサザンブロット分析を行い、欠失や重複の有無を調べる手法を推奨しています。
また、Kristjanssonら(1994年)は、プライマー伸長増幅(PEP)法を使用して、単一細胞レベルでの遺伝子診断を可能にし、DMDの診断範囲を広げました。
● 診断における臨床支援
Parsonsら(1996年)は、新生児スクリーニングを通じてDMDを早期に診断し、両親に告知する手法について検討しました。早期に正確な情報を提供することが、家族の精神的負担を軽減し、適切な支援につながるとしています。スクリーニングから診断に至るまで、家族には十分な選択肢と支援が提供されるべきであることが強調されています。
ヘテロ接合体
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)やベッカー型筋ジストロフィー(BMD)のヘテロ接合体保因者の診断は、さまざまな方法で行われていますが、確定診断には依然として課題が残っています。
Roses ら(1977年)は、乳酸脱水素酵素(LDH)のアイソザイム5が、クレアチンホスホキナーゼ(CPK)と同様に保因者状態の指標として非常に敏感であると報告しています。特に、CPKが正常値である一部の保因者でもLDH-5の上昇が確認されており、これを組み合わせた検査で高い保因者特定率を達成しました。さらに、ヘモペキシンのレベルも保因者の一部で上昇し、CPKと併用することで保因者検出が改善されることが示されています【パーシーら(1981年)】。
● 筋生検とジストロフィン検査
筋生検を用いたジストロフィンタンパク質の分析は、保因者診断に広く使われるようになっています。ジストロフィン遺伝子の異常を特定するためには、筋細胞におけるモザイク状のジストロフィン免疫染色パターンが重要です。これは、以前は肢帯型筋ジストロフィーと誤診されていた女性患者にも適用され、保因者であることが確認されています【Minetti et al., 1991】【Arikawa et al., 1991】。
Hoffmanら(1992年)による追跡調査では、ジストロフィン検査がDMD保因者である女性の特定に役立つことが明らかにされ、約10%の患者がこの検査によってDMD保因者であることが判明しました。このような女性患者は、正常なX染色体の優先的不活性化が原因で、筋ジストロフィーの症状が現れる可能性があるとされています。
● 血液検査とジストロフィン発現
ジストロフィン検査と血液検査の結果が一致しない場合や、クレアチンキナーゼ値が正常な場合でも、遺伝的検査や体細胞レベルでのジストロフィン発現の評価が有効であると考えられます。Hurkoら(1989年)は、ジストロフィン発現が体細胞レベルで検出されることが保因者診断に有用である可能性を示しました。
● 臨床的特徴と病理所見の関係
Hoogerwaardら(2005年)は、DMDおよびBMD保因者における骨格筋生検の結果を分析しましたが、筋力低下や心筋症、ジストロフィン異常と病理組織学的変化との明確な関連性は認められませんでした。興味深いことに、心筋症を発症している保因者でもジストロフィン異常は見られず、逆に症状がない保因者でジストロフィン異常が認められることもありました。
● 結論
DMDやBMDの保因者診断は、酵素測定、筋生検、遺伝子検査などを組み合わせることで進展してきましたが、特に無症候性の女性保因者の診断は依然として課題が残っています。
家族内変動
Sifringer ら(2004年)は、デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)患者の家族内での臨床経過の差異に関する調査を行いました。特に、同じDMD遺伝子に変異がないにもかかわらず、2人の兄弟で異なる病態が現れるというまれなケースに注目しました。
研究では、兄弟の発育や筋力低下の進行において顕著な違いが確認されました。例えば、弟は兄よりも9か月早く座ることができ、22か月も早く歩行が可能になったうえ、9歳になっても車椅子を必要としないことが予想されていました。一方で、兄はより重度の筋力低下に加え、精神発達障害も併発していました。
両者ともにジストロフィンの欠失や点変異は見つからなかったものの、免疫蛍光法による検査ではジストロフィンが陰性であり、ジストロフィン症であると診断されました。しかし、症状の軽い弟では代償メカニズムが働いている可能性が示唆されました。
Sifringer らは、兄弟の骨格筋におけるトランスクリプトーム(転写物)のプロファイルを比較し、軽度の症状に関連する可能性のある過剰発現遺伝子を特定しました。軽症の弟の筋肉では、6つの遺伝子が3倍から20倍の過剰発現を示し、特にカゼインキナーゼ1やミオシン軽鎖ポリペプチド2(MYL2)のアップレギュレーションが確認されました。これらは、筋線維の再生に関連する重要なマーカーであり、軽度の表現型に関連していると考えられています。
この研究の目的は、DMDの病態に影響を与える修飾因子を特定することで、治療法の開発に役立つ知見を得ることにありました。
治療・臨床管理
1. 歩行補助器具と身体機能の維持
Goertzen ら(1995年)は、DMD患者において、脊椎筋の早期解放、大腿筋膜張筋の切除、腓骨筋の伸長が、重度拘縮の予防や側弯症の進行遅延に有効であることを報告しています。これにより、患者の生活の質の改善を目指す治療が行われています。
2. 成長ホルモン阻害剤の使用
Zatz ら(1981年)は、成長ホルモン欠損症を併発したDMD患者が非常に軽度の症状を示したことに基づき、成長ホルモン阻害剤であるマゼンタールの使用を検討しました。その後、Zatzら(1986年)の双子の研究では、マゼンタールを投与された患者の方が症状が著しく改善し、プラセボ群よりも「症状が事実上停止」したという結果が得られました。
3. ステロイド療法
Mendellら(1989年)は、プレドニゾンの投与によりDMD患者の筋力が改善することを報告しました。プレドニゾンなどのコルチコステロイドは、DMDの管理において広く用いられており、筋力の維持や進行の遅延に効果があるとされています。しかし、副作用のために長期投与に関しては慎重な判断が必要です。
4. カルパイン阻害
カルパインの過剰活性が筋壊死と関連しているという仮説に基づき、SpencerとMellgren(2002)は、カルパイン阻害がDMDの治療法となる可能性を提唱しました。カルパインの活性化を抑制することで、筋細胞の壊死を防ぐアプローチです。
5. ゲンタマイシンによるリードスルー治療
Malik ら(2010年)は、ジストロフィン遺伝子の終止コドン変異を持つDMD患者に対して、ゲンタマイシンによる治療を行い、血清クレアチンキナーゼ値の50%減少を確認しました。ジストロフィンレベルの増加も一部の患者で見られ、筋力の維持や肺機能の改善が観察されました。この結果は、終止コドン変異に対するリードスルー療法としてのゲンタマイシンの有効性を示唆しています。
これらの治療法はDMDの進行を遅らせるための重要な手段となっており、特にステロイド療法や新しい分子レベルの治療が今後も注目されています。
遺伝子治療
デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)の遺伝子治療は、ジストロフィンの欠損を補うことを目的としたさまざまなアプローチが開発されています。以下は、遺伝子治療に関する主な研究内容です。
1. 筋芽細胞移植
Mendellら(1995年)は、DMD患者に筋芽細胞を移植することで、筋線維内にドナー由来のジストロフィンを発現させる試みを行いました。しかし、移植された筋芽細胞によるジストロフィン発現は低レベルに留まり、筋力の改善も限定的でした。
2. エクソンスキッピング
Van Deutekomら(2001年)やAartsma-Rusら(2003年)は、DMD患者においてエクソンスキッピング技術を用い、ジストロフィンのmRNAスプライシングを調節することで、リーディングフレームを修復し、BMD(軽度の筋ジストロフィー)のような状態に変換する方法を研究しました。これにより、ジストロフィン合成が回復し、細胞膜での機能が復元されました。特にエクソン51のスキップを誘導する技術は、患者の約16%に適用できると考えられています。
3. ミニジストロフィン・マイクロジストロフィン
Harperら(2002年)は、短縮型ジストロフィン(ミニジストロフィン、マイクロジストロフィン)を開発し、DMDモデルのマウスで機能回復を確認しました。短縮ジストロフィンは、筋肉損傷からの保護や形態学的な正常化に寄与し、アデノ随伴ウイルス(AAV)を用いた遺伝子導入が筋肉の状態を劇的に改善することが示されました。
4. リードスルー療法(PTC124)
Welchら(2007年)は、PTC124(アタラレン)という薬剤を開発し、早期終止コドンの読み越しを誘導することで、ジストロフィンの生成を回復させる治療法を提案しました。PTC124は、DMDのようなナンセンス変異を持つ遺伝性疾患におけるリードスルー治療として期待されています。
5. PRO051による治療
Aartsma-Rusら(2003年)やVan Deutekomら(2007年)は、アンチセンスオリゴヌクレオチド(PRO051)を用いてエクソン51をスキップし、DMD患者のジストロフィン発現を回復させる技術を研究しました。筋肉内注射によって64~97%の筋線維でジストロフィンが確認され、症状の改善が期待されました。
6. 免疫反応と自己免疫のリスク
Mendellら(2010年)は、T細胞免疫応答がジストロフィンの導入後に発生する可能性を報告しました。自然に発現するリバータントジストロフィンが自己反応性T細胞の標的になることがあり、これが遺伝子治療における免疫リスクとして考慮されています。
まとめ
DMDの遺伝子治療は、エクソンスキッピングやミニジストロフィン導入、リードスルー療法といったアプローチが研究されており、これらの技術は将来的に効果的な治療法となる可能性があります。ただし、免疫応答や治療の持続性などの課題も残されています。
細胞遺伝学
Greensteinら(1977年)は、X;11相互転座を有する16歳の少女でDMDが見つかり、この症例では母親は保因者ではないと考えられました。この場合、転座によるXp21の切断が、ヌル変異を引き起こし、正常なX染色体が不活性化されたことが原因であるとされます。さらに、Verellenら(1978年)やCankiら(1979年)は、X;21転座やX;3転座とXp21の切断を持つ類似のケースを報告しており、これらの症例でもX染色体の異常がDMDを引き起こしているとされています。
また、Zneimerら(1993年)は、リチャーズら(1990年)の報告をもとに、DMDの双子のX染色体に約300kbの欠失があることを確認し、分子細胞遺伝学的な技術を用いて正常なX染色体が不活性化されていることを示しました。これにより、患者におけるDMD遺伝子欠失の具体的なメカニズムが解明されました。
Saito-Oharaら(2002年)は、DMDと重度の精神発達障害、眼振などの神経症状を示す患者で、X染色体短腕逆位(inv(X)(p21.2q22.2))が確認されました。DMD遺伝子の一部の欠失に加え、PLP1遺伝子の重複やRAB40AL遺伝子の破壊が、神経および発達の問題を引き起こしている可能性が示唆されています。
Tranら(2013年)は、3歳の男児において、DMDと中程度の精神発達障害の関連を調査し、ジストロフィン遺伝子とKUCG1遺伝子がイントラクロマソーム逆位を持っていることを報告しました。KUCG1遺伝子は脳で発現する長鎖ノンコーディングRNAであり、その中断が発達障害に寄与している可能性が示唆されていますが、他の家族では変異は確認されていません。
これらの事例は、DMDの病因が単なる遺伝子変異にとどまらず、複雑な染色体異常や遺伝子破壊と関連していることを示しています。
分子遺伝学
さらに、Oshimaら(2009年)は、624例のインデックス症例のDMD変異について評価し、その中で238例(38.1%)にゲノム再編成が検出されたことを報告しています。これには188件の欠失(単一エクソン欠失が31例、複数エクソン欠失が157例)および44件の重複(単一エクソン重複が12例、複数エクソン重複が32例)が含まれます。さらに、6件の複雑な再配列も確認されています。
Oshimaらは、これらの再配列をさらに解析し、非相同末端結合(NHEJ)やテンプレートスイッチングなど、遺伝子再編成のメカニズムに関連する複数の要因を特定しました。特に、ブレークポイントの分析により、マイクロホモロジーや小さな挿入が見られたことから、DNA損傷の修復過程が再配列に関与している可能性が示唆されています。また、複雑な再配列の一部には、ステムループ構造や反復配列が関与しており、これらがゲノムの不安定性を引き起こす一因であるとされています。
修飾遺伝子
Pegoraroら(2011年)は、デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)の疾患進行に影響を与える修飾遺伝子を調査し、106人のDMD患者を対象に29の遺伝子の変異を解析しました。その結果、骨格筋のmRNAプロファイリングから、オステオポンチンをコードするSPP1遺伝子のプロモーター領域にあるrs28357094という変異が注目されました。このGアレルを持つ患者は、疾患進行がより速く、グルココルチコイド療法への反応も変化していることが確認されました。特に、Gアレルを持つ患者(対象者の35%)では、握力が12~19%低下しており、この影響は156人の患者による第2コホートでも確認されています。
また、Spitaliら(2020年)の研究では、極端な表現型を示すDMD患者の全エクソームシーケンスを行い、さらに2つのDMDコホートで検証したところ、TCTEX1D1遺伝子におけるrs1060575およびrs3816989の2つのSNPが、歩行不能になる年齢の早期化に関連していることが明らかになりました。これらのSNPは疾患進行に重要な影響を与える修飾因子として注目されています。
動物モデル
Williamsら(1983年)は、カナダのトロントにおけるDMDの発生率を男性出生100万人あたり292と推定し、発症例の3分の1が散発的なものであることを示しました。この結果は、男性と女性における突然変異率が同等であることを支持しています。
Mostacciuoloら(1987年)は、DMDおよびBMDの発症率と突然変異率を調査しました。また、MullerとGrimm(1986年)は、DMD家系におけるX染色体RFLP(制限断片長多型)を用いたハプロタイプ解析を行い、男女間の突然変異率の違いを評価しました。オランダのvan Essenら(1992年)は、DMDの出生時の発症率が男性新生児4,215人に1人であると推定し、1983年1月1日時点の有病率を男性18,496人に1人としています。
また、英国のRoddieとBundey(1992年)は、ウェスト・ミッドランズ地域でDMDの発症頻度がアジア系インド人では高く、パキスタン人では低いことを報告しました。彼らは、インド人におけるDMDの高頻度の原因として、変異を起こしやすい遺伝的要因が関与している可能性を示唆しています。
Shomratら(1994年)は、イスラエルのDMDおよびBMD患者におけるDMD遺伝子の欠失率が37%と、ヨーロッパや北米の55~65%に比べて低いことを発見しました。この欠失の割合の違いは、日本や中国などアジアの一部でも報告されており、欠失のサイズと病気の重症度には関連性がないとされています。
Onengutら(2000年)は、トルコ人、ヨーロッパ人、北インド人、インド全土の集団におけるDMD遺伝子欠失のパターンを比較し、欠失のサイズや頻度には小規模な違いがある一方、特定の欠失切断点の分布には集団間で有意な差は見られなかったことを報告しました。この結果は、イントロン配列の保存性が、異なる集団で同じ欠失を引き起こしている可能性を示唆しています。
マウスモデル
KrahnとAnderson(1994年)は、デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)のmdxマウスモデルにおいて、同化ステロイドによる治療が筋線維の損傷を増大させることを示しました。この研究では、ステロイドの使用が筋組織のさらなる悪化を引き起こす可能性があることが示唆されました。
一方、マンら(2001年)は、DMDに対する新たな治療アプローチとして、2′-O-メチルアンチセンスオリゴリボヌクレオチドを使用してジストロフィン前mRNAのスプライシングを修飾する方法を報告しました。この技術により、mdxマウスにおけるエクソン23の除去を誘導し、ジストロフィンの産生を促し、筋線維の修復を可能にしました。これにより、ジストロフィン欠損症に対してベッカー型筋ジストロフィーのような軽度の表現型を誘導できる可能性が示唆されています。
Bartonら(2002年)の研究では、インスリン様成長因子I(IGF1)の過剰発現がmdxマウスの筋肉機能を保護し、筋力の向上、筋線維の再生、アポトーシス(細胞死)の抑制につながることが示されました。この結果から、IGF1の導入がDMDの治療において有効な戦略となる可能性が示されました。
また、Gilbertら(2003年)は、ウイルスベクターを用いてジストロフィンを筋肉に導入する試みを行い、ジストロフィン陽性筋線維の回復を確認しました。さらに、筋細胞の構造的安定性が向上し、筋肉の損傷が軽減されたことが示されています。
Moghadaszadehら(2003年)は、ADAM12の過剰発現が筋変性を軽減し、筋肉再生を促進する効果を示しました。また、ユトロフィンやインテグリンの発現が増加し、筋膜の安定性が向上したことから、これらの分子がDMD治療の新しいターゲットになる可能性を示しました。
これらの研究により、遺伝子治療や分子標的治療が、DMDの進行を抑え、筋肉機能を維持するための有望な治療法として浮上しています。
Yueら(2004年)は、デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)を研究し、心筋細胞の50%で完全長のジストロフィン遺伝子を発現するヘテロ接合型mdxマウスを作製しました。このマウスモデルを使い、β-イソプロテレノール負荷試験を実施したところ、mdxマウスでは心筋細胞膜が損なわれる一方で、ヘテロ接合型mdxマウスや野生型マウスでは損なわれませんでした。このことから、心筋細胞の50%でジストロフィン遺伝子が発現すれば、DMDに伴う心筋症の治療に十分であることが示唆されました。
Wehling-Henricksら(2005年)は、DMDに関連する心疾患のモデルで、神経型一酸化窒素合成酵素(NOS1)遺伝子を導入することで心筋線維症と心筋炎の進行が抑制されることを示しました。この治療法により、mdxマウスに見られる心電図の異常も改善され、自律神経機能の欠陥も減少しました。
Cohnら(2007年)は、DMDのmdxマウスモデルにおいて、TGF-β活性の増加が筋肉再生不全と線維症を引き起こすことを実証しました。TGF-β中和抗体やロサルタンなどの薬剤を用いてTGF-βを抑制すると、筋肉の再生が促進され、筋力が改善しました。
Peterら(2009年)は、DMDマウスモデルで筋原性Aktシグナル伝達が促進されると、筋肉におけるユトロフィンの発現が増加し、ジストロフィンの機能を代替することで筋肉の消耗と損傷が軽減されることを示しました。
Bellingerら(2009年)は、mdxマウスのカルシウムチャネルの異常が筋損傷の一因であることを示し、カルシウム漏れを防ぐ薬剤であるS107が筋損傷を軽減し、筋機能を改善する可能性があると報告しました。
Iwataら(2009年)は、カルシウムチャネルのTrpv2を遺伝的に抑制することで、mdxマウスの筋肉のカルシウム濃度上昇が減少し、ジストロフィー性変化が改善されることを実証しました。
Liら(2009年)は、ジストロフィンとサルコグリカンが欠損したマウスで、筋疾患がさらに進行し、筋機能が低下することを示しました。また、マトリックスメタロプロテアーゼ-9(MMP9)の抑制が、筋再生を促進し、筋損傷を軽減する効果があることを示しました。
これらの研究により、遺伝子治療や薬理学的治療が、DMDの進行を遅らせる有望な手段として期待されています。
Wehling-Henricksら(2009年)は、神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS、NOS1)の欠損がデュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)モデルであるmdxマウスの易疲労性に関与しているかどうかを検証しました。彼らの研究では、nNOSを筋肉に導入することでmdxマウスの持久力が向上し、グリコーゲン代謝が促進されましたが、筋肉の血管灌流には影響を与えませんでした。さらに、nNOSは筋肉の解糖系の律速酵素であるホスホフルクトキナーゼ(PFK)の活性を促進し、解糖代謝を改善しました。この研究は、DMD患者に見られる易疲労性の一因が、nNOSとPFKのオールステリック相互作用の欠如による代謝障害である可能性を示唆しています。
また、三浦ら(2009年)は、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体PPAR-β/δのアゴニストであるGW501516が、DMDモデルであるmdxマウスにおいて、ユトロフィンAの発現を増加させ、筋細胞膜の安定性を改善することを発見しました。この治療により、筋線維の損傷が軽減し、筋機能が保護されました。
mdxマウスはDMDの研究モデルとして広く用いられていますが、mdxマウスでは筋線維の再生能力が高いため、ヒトDMDの症状を完全には再現していません。Saccoら(2010年)は、mdxマウスの軽度の表現型が、長いテロメアによって筋幹細胞の再生能力が高まっているためであることを示しました。さらに、テロメラーゼRNA構成要素(TERC)を欠く二重変異マウスでは、ヒトDMDにより近い重度の進行性筋ジストロフィーが発症し、これが筋幹細胞の機能低下によるものであるとされています。
Di Certoら(2010年)は、人工ジンクフィンガートランスクリプション因子(ZF ATF)を用いてユトロフィン発現を増加させる戦略を開発し、mdxマウスにおいて筋細胞膜の完全性を回復させ、ジストロフィー性疾患の進行を抑えることに成功しました。
さらに、Vermaら(2010年)は、血管密度を増加させることがDMDにおける筋組織の改善につながる可能性を示しました。彼らは血管密度を増加させるマウスモデルを作成し、筋肉の線維症や石灰化が減少し、筋力が改善することを発見しました。
Menazzaら(2010年)は、筋ジストロフィーにおけるモノアミン酸化酵素(MAO)の役割を調査し、MAOによってミトコンドリアで生成される活性酸素種(ROS)が、筋ジストロフィーの病態に関与していることを発見しました。彼らは、MAO阻害剤であるパルギリンを用いて、mdxマウスなどの筋ジストロフィーモデルにおいてROSの蓄積を減少させ、筋線維のアポトーシスを抑制し、筋力を改善することを報告しました。これにより、MAO阻害がDMD治療の潜在的なアプローチとなる可能性が示唆されました。
また、Villaltaら(2011年)は、DMDモデルであるmdxマウスにおけるマクロファージの役割を調査し、筋損傷を促進するM1マクロファージと、組織修復を促進するM2cマクロファージのバランスを制御する因子としてインターロイキン-10(IL-10)を特定しました。IL-10がM1マクロファージの活性化を抑え、M2cマクロファージの活性化を促進することで、筋肉の分化と修復に貢献することが明らかとなり、筋ジストロフィーの病態における重要な役割が示されました。
Gehrigら(2012年)は、筋ジストロフィーモデルにおいて、ヒートショックタンパク質72(Hsp72)の発現を増加させることで、筋力を維持し、筋病理を改善できることを発見しました。Hsp72の薬理学的誘導剤であるBGP-15の投与により、mdxマウスおよび重症型ジストロフィーモデルであるdkoマウスの筋機能が改善し、寿命が延長しました。BGP-15は、サルコメア/小胞体カルシウムポンプ(SERCA)の活性を維持し、筋肉の変性を減少させました。
Tjondrokoesoemoら(2016年)は、筋ジストロフィーにおけるカテプシンS(CTSS)の役割を研究し、mdxマウスにおけるCTSSの欠失が筋線維の膜安定性を改善し、疾患の進行を遅らせることを発見しました。CTSSの欠失により、筋線維壊死や線維化が減少し、走行能力が向上しました。CTSSは、筋膜の安定性を低下させることで病態に寄与しており、その抑制がDMDの新たな治療戦略となる可能性があります。
これらの研究は、筋ジストロフィーにおけるさまざまな分子メカニズムを標的とした治療の可能性を示しており、今後の治療法開発に重要な示唆を与えるものです。
イヌのモデル
SheltonとEngvall(2005年)は、デュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)のイヌモデルがゴールデンレトリバー、ビーグル、ロットワイラー、ジャーマンショートヘアードポインター、日本スピッツで報告されていると述べています。これらの犬種は、それぞれDMDに似た筋疾患のモデルとして使用されており、特にゴールデンレトリバーのDMDモデルが広く研究されています。
Sampaolesiら(2006年)は、ゴールデンレトリバーのDMD犬モデルが、ジストロフィン遺伝子の変異によってヒトDMDの全病理学的特徴を正確に再現する唯一の動物モデルであると指摘しています。この犬種では、イントロン6にある突然変異によりジストロフィンが完全に欠失し、筋変性が早期に発症し、重度の筋力低下と運動障害が見られます。このモデルは、呼吸筋の機能不全により通常1歳前後で死亡します。彼らの研究では、野生型イヌ由来の中胚葉系幹細胞を動脈内に注入した結果、ジストロフィンの発現が回復し、筋肉の形態と機能が改善され、臨床的な運動能力が著しく向上したことが確認されました。この成果は、将来のDMD治療において幹細胞療法が有望であることを示唆しています。
Amoasiiら(2018年)は、アデノ随伴ウイルス(AAV)を用いてCRISPR遺伝子編集技術をDMDのデルタE50-MD犬モデルに適用しました。彼らは4匹の犬にこの技術を導入し、2匹には筋肉内投与、残りの2匹には全身投与を行い、その後ジストロフィンタンパク質の発現を調べました。筋肉全体でジストロフィンレベルが正常値の3~90%まで回復し、心筋では最高92%の回復が確認されました。これにより、筋組織の改善も認められ、CRISPRによる遺伝子編集がDMD治療において臨床的に有用である可能性が示されました。
ネコのモデル
Winand ら(1994年)は、筋ジストロフィーを患う短毛種の雄ネコにおいて、ジストロフィンプロモーターの欠失を発見しました。このネコは、全身性の筋肥大、硬化、軽度の組織病理学的ジストロフィーを示しました。この突然変異により、筋ジストロフィンとプルキンエ細胞ジストロフィンの発現が完全に消失しました。一方、皮質ニューロン型ジストロフィンは骨格筋では発現していたものの、心臓では検出されませんでした。
SheltonとEngvall(2005年)は、DMDのネコモデルについても言及しており、ネコがデュシャンヌ型筋ジストロフィーの研究において有用なモデルとなることを指摘しています。ネコモデルは、ヒトと似た筋病理や発症機序を示すため、DMD治療の前臨床研究において重要な役割を果たしています。
ゼブラフィッシュモデル
BassettとCurrie(2003年)は、ゼブラフィッシュを用いた筋ジストロフィーおよび先天性ミオパチーのモデルをレビューしました。ゼブラフィッシュは、遺伝子操作が比較的容易であり、筋疾患の発症メカニズムや治療法の研究において重要なモデル生物です。特にゼブラフィッシュは、その胚発生過程が短く、透明な胚を観察することで、筋形成や疾患の進行をリアルタイムで追跡できるという利点があります。
ゼブラフィッシュモデルでは、ヒトのデュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)に類似した遺伝子変異を導入することができ、これによりジストロフィンの欠損や筋線維の壊死が引き起こされます。これにより、ゼブラフィッシュはDMDなどの筋疾患の発症機構や治療法の検証に用いられ、薬剤スクリーニングや遺伝子治療の評価にも役立つモデルとして広く研究されています。