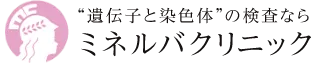目次
SDHC遺伝子
SDHC遺伝子産物は、ヘム結合活性があると予測。コハク酸からユビキノンへのミトコンドリア電子輸送に関与すると予測。ミトコンドリア内膜に存在すると予測。ミトコンドリア呼吸鎖複合体II、コハク酸脱水素酵素複合体(ユビキノン)の一部であると予測。Carney-Stratakis症候群、消化管間質腫瘍、肺非小細胞癌、傍神経節腫に関与。
承認済シンボル:SDHC
遺伝子名:succinate dehydrogenase complex subunit C
参照:
HGNC: 10682
遺伝子OMIM番号602413
Ensembl :ENSG00000143252
AllianceGenome : HGNC : 10682
遺伝子のlocus type :タンパク質をコードする
遺伝子のグループ:Mitochondrial complex II: succinate dehydrogenase subunits
遺伝子座: 1q23.3
SDHC遺伝子の機能
SDHC遺伝子は、ミトコンドリアのトリカルボン酸サイクルと好気性呼吸鎖の重要な酵素複合体である、ミトコンドリア複合体IIとしても知られるコハク酸デヒドロゲナーゼを構成する4つの核内コードサブユニットのうちの1つをコードしている。コードされているタンパク質は、触媒コアを形成する複合体の他のサブユニットをミトコンドリア内膜に固定する、2つの膜タンパク質のうちの1つである。この遺伝子にはいくつかの関連偽遺伝子が異なる染色体上に存在する。この遺伝子の変異は傍神経節腫と関連している。交互にスプライシングされた転写産物の変異体が報告されている。2013年5月、RefSeqより提供。
SDHC遺伝子の発現
腎臓(RPKM 80.5)、肝臓(RPKM 66.7)、その他25の組織にユビキタスに発現
SDHC遺伝子と関係のある疾患
※OMIIMの中括弧”{ }”は、多因子疾患または感染症に対する感受性に寄与する変異を示す。[ ]は「非疾患」を示し、主に検査値の異常をもたらす遺伝的変異を示す。クエスチョンマーク”? “は、表現型と遺伝子の関係が仮のものであることを示す。
Gastrointestinal stromal tumor 消化管間質腫瘍
606764
AD(常染色体優性) IC 3
SDHBを参照のこと。
Paraganglioma and gastric stromal sarcoma パラガングリオーマ(傍神経節腫瘍)と消化管間質腫瘍
Paragangliomas 3 傍神経節腫3
605373
AD(常染色体優性) 3
遺伝性傍神経節腫-3(PGL3)は、コハク酸デヒドロゲナーゼ複合体のサブユニットCをコードする染色体1q23上のSDHC遺伝子(602413)のヘテロ接合体変異によって起こる。
傍神経節腫は「グロムス小体腫瘍」とも呼ばれ、全身に存在する傍神経節に由来する腫瘍である。非クロマフィン型は主に化学受容器として機能し(それゆえ、腫瘍名は「化学線腫」である)、頭頸部(すなわち、頸動脈小体、頸静脈、迷走神経および鼓膜領域)に存在するのに対し、クロマフィン型は内分泌活性を有し、従来は「褐色細胞腫」と呼ばれ、通常、頭頸部より下(すなわち、副腎髄質および前胸腹部および傍胸腹部領域)に存在する。PGLは、非クロマフィン頭頸部腫瘍のみ、副腎および/または副腎外褐色細胞腫のみ、または2つのタイプの腫瘍の組み合わせとして発現しうる(Baysal、2002;Neumannら、2004)。
胃平滑筋肉腫、肺軟骨腫、および副腎外傍神経節腫の3徴候は、主に若年女性に発現する症候群を構成し、Carney triad (604287)として知られる。この三徴候は、粘液腫、斑状色素沈着、内分泌異常の他のCarney症候群(160980)と混同してはならない。
Baysal (2008) は、遺伝性傍神経節腫の分子病態について概説している。
傍神経節腫の遺伝的不均一性
染色体1p36上のSDHB遺伝子(185470)の変異が原因のPGL4(115310);染色体1q21上のSDHC遺伝子(602413)の変異が原因のPGL3(605373);染色体11q13上のSDHAF2遺伝子(613019)の変異が原因のPGL2(601650)も参照のこと; 染色体5p15上のSDHA遺伝子(600857)の変異に起因するPGL5(614165)、染色体17p13上のSLC25A11遺伝子(604165)の変異に起因するPGL6(618464)、染色体14q24上のDLST遺伝子(126063)の変異に起因するPGL7(618475)。
臨床的特徴
Krollら(1964年)は、常染色体優性遺伝の家族12人に頸動脈小体腫瘍を認めた。Reslerら(1966年)は、両側の頸動脈小体腫瘍および頸静脈腺腫を有する患者を報告した。著者らは、家族性頸動脈小体腫瘍は多発する傾向があることを指摘した。家族性頸静脈腺腫は、1937年にGoekoop(引用:Rosen、1952)により報告された3人の罹患した姉妹にみられた。LadenheimとSachs (1961)も参照のこと。Bartels(1949)は、連続する3世代の家族において頸動脈小体腫瘍を同定した。
Wilson(1970)は、頸動脈小体型腫瘍の家族性報告をレビューし、男性から男性への伝播と飛び火を伴う家族について記述した。Pratt(1973年)は文献をレビューし、4世代にわたる血族に片側または両側の頸動脈小体腫瘍が新たに8例発生したことを報告した。この家系の1世代において、4人の姉妹が両側性腫瘍を、1人の兄弟が片側性腫瘍を有していた。報告された8例の腫瘍はいずれも悪性ではなかった。ChedidおよびJao(1974年)は、連続する2世代の家族の6人に頸動脈小体腫瘍を同定した。4人は慢性閉塞性肺疾患でもあり、動脈pCO(2)が持続的に高く、pO(2)が低かった。著者らは、腫瘍はこれらの変化した血液ガスの刺激による二次的な過形成として始まったと推論した。Nissenblatt(1978)は、28歳で頸動脈小体腫瘍を発症した右心低形成症候群の若い女性を報告した。彼は、高所生活、肺気腫、チアノーゼ性先天性心疾患などの低酸素状態と頸動脈小体腫瘍の発生との関連を示唆した。
Gruffermanら(1980年)は、頸動脈小体腫瘍を有する2人の姉妹を報告し、家族性CBT症例88例と非家族性CBT症例835例の報告を検討した。家族性症例は男女比が等しく、常染色体優性遺伝に従った。両側性疾患は家族性症例の31.8%、散発性症例の4.4%にみられた。全患者の6%が二次原発腫瘍を発症し、そのほとんどが他の傍神経節腫であった。Parryら(1982年)は、頸動脈小体腫瘍の組織学的に診断された222例の記録をレビューし、その内訳は女性146例、男性76例であった。腫瘍発生時の平均年齢は44.7歳であった。多発性原発腫瘍症候群を示唆する他の副腎外傍神経節腫を有する16人の患者では、診断がより早く起こった(平均、35.4歳;pは0.01未満)。5人の患者は甲状腺がんも発症した。家族性症例は両側性であることが多く、診断がわずかに早かった。
Van Baarsら(1982年)は、家族性非クロマフィン傍神経節腫に関する文献のレビューを提供した。頸動脈小体腫瘍が最も多く、次いで頸静脈腺腫、迷走神経腺腫、および鼓膜腺腫であった。
Parkin(1981年)は、頭頸部の多発性グロムス腫瘍を伴う褐色細胞腫の遺伝性症候群を有する血縁関係のない2家系を報告した。DeAngelisら(1987年)は、神経線維腫症(162200)の患者における褐色細胞腫および多発性傍神経節腫の発生を報告した。Karasovら(1982年)は、13~17歳の間に21個の傍神経節腫が摘出され、腫瘍が残存している証拠を伴う記録的な数の少女の散発性症例を記載した。腫瘍はカテコールアミン産生性であった。Khafagiら(1987年)は、血縁関係のない成人2人を報告しており、両者とも傍神経節腫の家族歴が陽性であった。両者とも悪性の非機能性傍神経節腫で、ヨウ素131メタヨードベンジルグアニジンの取り込みにより検出された;この薬剤は切除不能な転移の管理において治療価値があることが証明された。
Van Schothorstら(1998年)は、オランダの同じ地域に由来する頭頸部傍神経節腫を有する10家族を報告した。頸動脈分岐部が最も頻繁に侵される部位であり(頭頸部腫瘍全体の57%)、多発性傍神経節腫が患者の66%に発生した。異なる家系の患者3人が褐色細胞腫を発症した。女性保因者の罹患子孫は観察されず、罹患家族全員が父親から疾患遺伝子を受け取った。
Pronteraら(2008年)は、PGL1を有するイタリア人家族を報告した。プロブランドは49歳の男性で、咽頭痛、発声困難、呼吸困難、および軽度の高血圧を呈し、多発性の高血管性喉頭および頸動脈傍神経節腫を伴う両側頸動脈化学デクトーマが発見された。家族歴から、肺癌のため71歳で死亡した父親は、66歳のときに両側の頸動脈周囲傍神経節腫と診断された。推定者の55歳の姉は52歳の時に多発性の喉頭傍神経節腫と頸動脈傍神経節腫を発症した。プロブランドとその姉妹はともにSDHD遺伝子にヘテロ接合性の切断型変異を有していた。
Hensenら(2010)は、SDHD遺伝子の創始者変異(D92Y;602690.0004)に起因するPGL1を有する7世代にわたるオランダの大家族(Oosterwijkら、1996)の243人のメンバーにおいて、Kaplan-Meier法を用いて傍神経節腫の年齢特異的浸透率を算出した。発症年齢は14歳から47歳であった。臨床的徴候と症状のみで、浸透率は47歳までに最大57%に達した。MRIによる潜伏性傍神経節腫の検出を含めると、浸透度は40歳までに54%、60歳までに68%、70歳までに87%と推定された。複数の腫瘍が65%に認められ、傍神経節腫患者の8%が褐色細胞腫を有していた。1例(3%)が悪性傍神経節腫を発症した。11例の母体からの突然変異の伝播のうち、傍神経節腫の発症に至ったものはなかった。Hensenら(2010年)は、この研究における浸透率は以前の推定値よりも低かったと述べているが、この所見から、変異保因者の大多数が最終的に頭頸部傍神経節腫を発症することが示された。Hensenら(2010年)は、臨床的に罹患していない変異保因者を導入率の推定に含めることの重要性を強調している。
身体診察またはMRIによってスクリーニングされた47人の無症候性SDHD変異保因者のうち、Heestermanら(2013年)は、28人(59.6%)が頸動脈小体腫瘍38個、迷走神経小体腫瘍17個、頸動脈小体腫瘍2個を含む合計57個の腫瘍を保有していることを明らかにした。多発性腫瘍は患者の34%にみられた。2例(4.3%)に交感神経傍神経節腫がみられた。この報告は、無症候性SDHD遺伝子変異保因者の高い割合に潜伏性頭頸部傍神経節腫が存在することを示している。