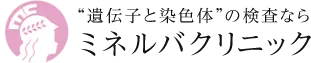目次
TSC1遺伝子
遺伝子名: TSC COMPLEX SUBUNIT 1; TSC1
別名: TSC1 GENE
HAMARTIN
染色体: 9
遺伝子座: 9q34.13
遺伝カテゴリー:Rare Single Gene variant-Syndromic
関連する疾患:Focal cortical dysplasia, type II, somatic 607341
Lymphangioleiomyomatosis 606690
Tuberous sclerosis-1 191100
TSC1遺伝子の機能
TSC1遺伝子は、チューブリンの安定化に役割を果たすと考えられている成長抑制タンパク質をコードしており、腫瘍抑制因子としての役割が示唆されている。
TSC1遺伝子は、チューブリン(TSC2;191092)と相互作用して、mammalian target of rapamycin 哺乳類ラパマイシン標的(MTOR;601231)の下流エフェクターへのシグナル伝達を阻害するタンパク質複合体を形成するタンパク質であるHamartinをコードしている(Inoki et al.
結節性硬化症-1で欠損しているタンパク質であるHamartin(TSC1)は、RAP1(600278)やRAB5(179512)の推定GTPase-activating proteinである結節性硬化症-2で欠損しているタンパク質であるtuberin(TSC2;191092)とは、有意な相同性はないとされている。しかし、Van Slegtenhorstら(1998)は、hamartinとtuberinがin vivoで物理的に会合しており、その相互作用は予測されたコイルドコイルドメインによって媒介されていることを示した。このデータは、hamartinとtuberinが別々の経路ではなく、同じ複合体で機能していることを示唆していた。
Benvenutoら(2000)は、TSC1遺伝子をラットの線維芽細胞に過剰発現させると、成長が阻害され、細胞の形態が変化することを示した。成長の阻害は、内因性のチューベリンレベルの上昇と関連していた。tuberinの過剰発現は細胞の成長を阻害し、hamartinはtuberinと結合することが知られていることから、これらの結果はhamartinがtuberinを安定化させ、これが細胞の成長阻害に寄与していることを示唆している。この安定化は、tuberinが細胞内で高度にユビキチン化されているのに対し、hamartinに結合しているtuberinの一部はユビキチン化されていないことから説明された。tuberinを共発現させると、ユビキチン化が弱いhamartinが一過性にトランスフェクトされた細胞で安定化した。tuberinのアミノ末端の3分の2は、ユビキチン化とhamartinの安定化に関与していた。TSC2遺伝子のミスセンス変異を持つ患者から得られたチューベリンの変異体N1658Kもまた、高度にユビキチン化されており、hamartinを安定化させることができなかった。Benvenutoら(2000)は、hamartinは成長を阻害するタンパク質であり、その生物学的効果はおそらくtuberinとの相互作用に依存していると結論づけている。
Hodgesら(2001)は、一連のhamartinとtuberinのコンストラクトを用いて、酵母2-hybridシステムでの相互作用をアッセイした。その結果、Hamartin(アミノ酸302-430)とTuberin(アミノ酸1-418)は互いに強く相互作用した。tuberinの推定コイルドコイルをコードする領域(アミノ酸346-371)は、Hamartinとの相互作用を媒介するのに必要であったが、十分ではなく、さらにN-末端側の残基も必要であった。また、コイルドコイルをコードすると予測されるhamartinの領域(アミノ酸719-998)は、オリゴマー化が可能であったが、tuberinとの相互作用には重要ではなかった。結節性硬化症の患者で確認された、HamartinまたはTuberinの結合領域内にある微妙な非切断型の突然変異は、これらのタンパク質の相互作用を消失または劇的に減少させた。
Milolozaら(2000)は、免疫ブロット分析によって測定されたhamartinの発現は、進行中の細胞周期全体を通して発現しているにもかかわらず、G0-arrested細胞で高くなることを示した。さらに、高レベルのhamartinを異所性で発現させると、細胞増殖が抑制された。著者らは、hamartinがG1期の制御を介して細胞増殖に影響を与えることを提案した。
活性化されたezrin (123900), radixin (179410), moesin (309845) (ERM)ファミリータンパク質は、内在性膜タンパク質とF-アクチンなどの細胞骨格タンパク質との結合を促進する(ACTA1; 102610参照)。不活性型では、ERMタンパク質のN末端とC末端が相互に作用して、それぞれの膜およびアクチンとの相互作用を隠している。ERMタンパク質の活性化にはRHO(ARHA; 165390参照)が必要であり、ERMタンパク質のC末端のスレオニンがリン酸化され、N末端とC末端の間の分子内結合が解かれるというカスケードが誘発される(Fukuhara and Gutkind, 2000)。Lambら(2000)は、酵母2ハイブリッド分析を用いて、エズリンを餌としたマウス線維芽細胞cDNAライブラリーをスクリーニングした。スロットブロット解析、免疫沈降法、免疫蛍光顕微鏡法、突然変異解析の結果、エズリンのN末端はhamartinのC末端と相互作用するが、merlin(607379)とは弱い相互作用しかなく、ジャイアントイン(602500)とは全く相互作用しないことがわかった。hamartinはradixinとmoesinのN末端とも相互作用していた。免疫蛍光顕微鏡で見ると、hamartinはF-actinと相互作用していることがわかり、hamartinがERMタンパク質の直接の結合相手である可能性が示唆された。hamartinをmicroscale chromophore-assisted laser inactivation (micro-CALI)やantisense hamartinで不活性化すると、内皮細胞膜の患部が著しく後退し、接着力が失われ、細胞が丸くなった。細胞の接着は、活性型RHOを注入することで回復することができた。アクチンフィラメントが組織化されていない細胞にhamartinを発現させると、フォーカルアドヒージョンの形成が促進され、アクチンストレスファイバーの形成も促進された。この活性にはRHOとhamartinの145から510番の残基が必要であった。hamartinのC末端フラグメントを導入すると、RHOを活性化する血清因子であるリゾホスファチジン酸によるアクチンストレスファイバーの形成が阻害されたことから、hamartinとERMタンパク質との相互作用はRHOの上流で必要であることが示唆された。Lambら(2000)は、hamartinの機能が失われたり阻害されたりすると、細胞マトリックスへの接着力が失われ、TSC hamartomaの発生が始まると提唱した
Taponら(2001)は、ショウジョウバエのTsc1およびTsc2(gigas)遺伝子の突然変異を特徴づけた。いずれの遺伝子にも不活性化変異があると、成長が促進され、細胞サイズが大きくなるという特徴を持つ同一の表現型が生じるが、細胞数には変化がなかった。全体的に、変異した細胞はG1にいる時間が短かった。Tsc1とTsc2の両方を共発現させると、組織の成長が制限され、細胞サイズと細胞増殖が減少した。この表現型は、サイクリンレベルを操作することで変化した。Tsc1とTsc2を共発現させると、組織の成長が制限され、細胞の大きさや増殖が低下した。このことは、ヒトの病変で観察されるように、これらの細胞が細胞周期に不適切に再突入する傾向と相関していた。
Potterら(2001年)は、ショウジョウバエのTsc1遺伝子に変異があることを突き止めた。Tsc1の変異体の細胞は、サイズが劇的に増大したが、正常に分化した。Tsc1変異細胞を多く含む組織では、臓器のサイズも大きくなっていた。イメージディスク内のTsc1変異細胞のクローンは、さらに分裂を繰り返したが、正常な細胞数を保っていた。Potterら(2001)は、Tsc1タンパク質がショウジョウバエのTsc2とin vitroで結合することも示した。Tsc1またはTsc2を単独で翅と眼に過剰発現させても効果はなかったが、共重発現させると、細胞サイズ、細胞数、器官サイズが減少した。遺伝的エピスタシスのデータは、Tsc1とTsc2がインスリン(INS;176730)シグナル経路で共に機能するというモデルと一致した。
Inokiら(2002)は、Tsc1-Tsc2複合体が哺乳類ラパマイシン標的(MTOR;601231)を阻害し、p70リボソームS6キナーゼ-1(608938)の阻害と、真核生物翻訳開始因子4E結合タンパク質-1(EIF4EBP1;602223)の活性化につながることを示した。
Astrinidisら(2006)は、ヒトおよび非ヒトの複数の細胞株において、内因性のポロライクキナーゼ-1(PLK1; 602098)がhamartin-tuberin複合体と結合し、その複合体が中心体に局在することを明らかにした。リン酸化されたhamartinは、tuberinとは独立してPLK1と相互作用し、その相互作用にはhamartinのthr310が必要であった。Hamartinは、PLK1のタンパク質レベルを負に制御し、MTOR依存的に中心体の数を制御した。Hamartinを欠損させたマウス胚性線維芽細胞では、中心体の数が増加し、DNA量の増加を伴う有糸分裂の欠陥が見られたが、これらの欠陥はラパマイシンで回復した。
TSC遺伝子の欠損は、MTORおよび下流のシグナル伝達要素の構成的な活性化をもたらし、その結果、腫瘍の発生、神経障害、および重度のインスリン/IGF1(147440)抵抗性を引き起こす。Ozcanら(2008)は、細胞株やマウスまたはヒトの腫瘍でTSC1またはTSC2が欠損すると、小胞体(ER)ストレスが生じ、アンフォールドタンパク質応答が活性化されることを発見した。その結果、小胞体ストレスは、MTORを介したインスリン作用の負のフィードバック阻害に重要な役割を果たし、アポトーシスに対する脆弱性を増大させていた。
Choiら(2008)は、Tsc1とTsc2がマウスの軸索の形成と成長に重要な機能を持つことを示した。Tsc1/Tsc2を過剰に発現させると軸索の形成が抑制され、Tsc1またはTsc2を欠損させると、in vitroおよびマウス脳内で異所性軸索が誘導された。Tsc2は樹状突起ではなく軸索でリン酸化され抑制されていた。Tsc1/Tsc2の不活性化は、少なくとも部分的には神経極性サッドキナーゼ(BRSK2; 609236参照)のアップレギュレーションを介して軸索の成長を促進したが、このキナーゼはTSC患者の皮質の塊茎でも上昇していた。Choiら(2008)は、TSC1とTSC2は神経細胞の極性に重要な役割を果たしており、共通の経路が神経細胞の極性や成長、他の組織の細胞サイズを制御していると結論づけている。
また、Parkら(2008)は、軸索の再生に内在する障害の役割を調べるため、ウイルスを用いたin vivoコンディショナルノックアウト法で細胞成長制御遺伝子を解析した。野生型の成体マウスでは、軸索を切断した網膜神経節細胞でmTOR活性が抑制され、新たなタンパク質合成が損なわれており、これが再生不全の原因になっていると考えられた。mTOR経路の負の制御因子であるTSC1を条件付きでノックアウトしてこの経路を再活性化すると、軸索の再生につながった。
DiBellaら(2009)は、ゼブラフィッシュのTSC1aをモルフォリーノでノックダウンすると、腎臓の嚢胞形成や左右非対称性を含む繊毛の表現型が生じることを示した。Tsc1aはゴルジ体に局在していたが、Tsc1aをノックダウンしたモルフォリノは、毛様体遺伝子と合成的に作用して、腎臓の嚢胞を形成した。Tsc1aはゴルジ体に局在していたが、Tsc1aに対するモルフォリンは毛様体遺伝子と合成的に作用して腎嚢を生成した。毛様体がTsc遺伝子と同じ経路で役割を果たしていることを示唆するように、毛様体変異体ではTOR (FRAP1; 601231) 経路が異常に活性化されており、Tsc1aノックダウンの効果と似ていた。ciliary変異体における腎臓の嚢胞形成は、TOR阻害剤であるラパマイシンによって阻害された。DiBellaら(2009)は、繊毛とTOR経路の間のシグナルネットワークを示唆しており、繊毛のシグナルがTOR経路に供給され、Tsc1aが繊毛自体の長さを調節しているのではないかと考えている。
Hartmanら(2009)は、Hamartin(TSC1)が一次繊毛の基底部に局在し、TSC1-nullおよびTSC2-nullのマウス胚線維芽細胞(MEF)は、野生型の対照細胞に比べて一次繊毛を含む可能性が有意に高いことを報告した。さらに、Tsc1-nullおよびTsc2-nullのMEFの繊毛は、野生型MEFの繊毛に比べて17~27%長かった。Tsc1-およびTsc2-null MEFの繊毛形成の促進は、ラパマイシンでは無効化されなかったことから、mTORに依存しないメカニズムであることが示唆された。Polycystin-1 (PC1; 601313参照)はTSC2と相互作用することがわかっているが、Pkd1-null MEFでは毛様体形成が促進されなかった。ADPKD患者の腎嚢ではmTORの活性化が観察されているが、Pkd1-null MEFでは、構成的なmTOR活性化の証拠がなく、これにより、一次繊毛とmTORの制御におけるTSCタンパク質とPC1の独立した機能が明らかになった。
Zhangら(2014)は、マウスやヒトの細胞でmTORC1を活性化すると、タンパク質合成が増加するだけでなく、タンパク質分解能力の向上も促進されることを示した。mTORC1が活性化された細胞では、プロテアソームサブユニットをコードする遺伝子の発現が全体的に増加することで、無傷かつ活性なプロテアソームのレベルが上昇した。プロテアソーム遺伝子の発現量、細胞内のプロテアソーム量、mTORC1下流のタンパク質ターンオーバー速度の増加は、すべて転写因子NRF1 (NFE2L1; 163260)の誘導に依存していた。結節性硬化症複合体の腫瘍抑制因子TSC1またはTSC2(191092)の欠損によるmTORC1の遺伝的な活性化、あるいは成長因子や摂食に応じたmTORC1の生理的な活性化により、細胞や組織におけるNRF1の発現が増加した。Zhangら(2014)は、このNRF1に依存したプロテアソームレベルの上昇が、細胞内のアミノ酸プールを増加させる役割を果たし、それによって新たなタンパク質合成の速度に影響を与えることを発見した。そこで著者らは、mTORC1シグナルがプロテアソームを介したタンパク質分解の効率を上げることで、品質管理と持続的なタンパク質合成のための基質供給メカニズムの両方を実現していると結論づけている。
TSC1遺伝子の発現
van Slegtenhorstら(1997)は、結節性硬化症-1(191100)の変異遺伝子を同定するための包括的な戦略の一環として、9番染色体上の1.4MbのTSC1領域からクローンのオーバーラップするコンティグを開発した。いくつかの手法により、この領域は遺伝子が豊富であり、900kbのセグメントに少なくとも30の遺伝子が存在することが示された。その結果、D9S1199とD9S114の間に142のエクソンと13の遺伝子が同定された。著者らは、40人の散発性結節性硬化症患者と20人の無関係な家族性結節性硬化症患者から採取した60のDNAサンプルにおいて、推定エクソンと確認エクソンをPCRで増幅し、9q34との関連を示した。Van Slegtenhorstら(1997)は、以前の遺伝子発見活動(Nagaseら、1996)によって同定された転写ユニットの一部であるエクソンに変異を同定した。van Slegtenhorstら(1997)が「hamartin」と呼んだ予測されるTSC1タンパク質は、1,164個のアミノ酸からなり、計算上の質量は130kDである。
TSC1遺伝子と自閉症スペクトラム障害ASDの関係
TSC1遺伝子は、特定の症候群を持つ人の一部が自閉症を発症する症候性自閉症と関連している。特に、自閉症と結節性硬化症(したがって、TSC1およびTSC2遺伝子も同様)との間には遺伝的な関連がある。
TSC1遺伝子とその他の疾患との関係
結節性硬化症
Van Slegtenhorstら(1997)は、結節性硬化症の患者において、第9染色体上の1.4MbのTSC1領域のエクソンをスクリーニングし、変異を調べた。TSC1遺伝子の1つのエクソンには、60人の患者のうち10人のサンプルのヘテロ二重解析で移動度の変化が認められた。配列解析の結果、7つの小さなフレームシフト変異(例:605284.0001)、1つのナンセンス変異(605284.0002)、1つのミスセンス変異(605284.0003)、そしてコードされるアミノ酸を変えない1つの多型が見つかった。最初のスクリーニングで高い頻度で変異が見つかったのはエクソン15でした。エクソン15は559bpの長さで、コーディング領域の16%を占める。エクソン15に変異が見つかったのは、結節性硬化症の55家系のうち、9q34との連鎖が認められた8家系(15%)であり、連鎖が認められなかった散発性患者や家系では607家系のうち15家系(2.5%)のみであった。家族性症例20人と散発性患者152人を対象に、すべてのコーディングエクソンに変異があるかどうかを調べたところ、それぞれ8つの変異が見つかった(それぞれ40%と5%)。TSC1に発見された32個の変異のうち、30個は切断型で、1個の変異(2105delAAAG; 605284.0001)は、明らかに血縁関係のない6人の患者に見られた。この6名のうちの1名では、結節性硬化症に伴う腎癌に野生型対立遺伝子の体細胞変異が見られ、hamartinが癌抑制因子として働くことが示唆されました。
Jonesら(1997)は、171名の連続したTSC患者を対象に、21個のコード化された全エクソンのSSCPとヘテロデュープレックス解析、および遺伝子座全体に及ぶ制限断片のアッセイを行い、TSC1の変異スペクトルを包括的に定義した。その結果、家族性の場合は24例中9例に変異が認められたが、散発性の場合は147例中13例にとどまった。一方、限定的なスクリーニングでは、24人の家族性症例のうち2人、147人の散発性症例のうち45人にTSC2遺伝子の変異が認められた。このように、TSC1遺伝子の変異は、散発性症例の中で著しく少ないことがわかった。TSC2遺伝子座には大きな欠失とミスセンス変異の両方がよく見られたが、TSC1遺伝子の変異の多くは小さな切断病変であった。精神遅滞は、TSC1遺伝子変異の保因者ではTSC2遺伝子変異の保因者よりも有意に少なかった(散発例のみのオッズ比5.54、多世代家族ごとに無作為に選ばれた1人の患者を加えた場合は6.78±1.54)。精神遅滞と変異の種類との間に相関関係は認められなかった。Jonesら(1997年)は、結節性硬化症-1では結節性硬化症-2と比較して精神遅滞のリスクが低く、その結果生じる確認バイアスが、散発性TSCにおけるTSC1変異の相対的な少なさを少なくとも部分的に説明していると結論づけている。
Kwiatkowskaら(1998年)は、TSC1領域に遺伝的なつながりのある13家族、つながりのない22の小家族、および126人の散発性患者を対象に、サザンブロット分析、増幅されたエクソンのSSCPおよびヘテロデュープレックス分析を用いて、TSC1遺伝子の変異に関する包括的な分析を行った。その結果、21人の患者に17個のユニークな変異が確認された。変異は、結節性硬化症-1に関連する13家系のうち7家系(54%)、連鎖情報のない小家系22家系のうち1家系(5%)、および126名の散発例のうち13名(10%)に認められた。変異はすべて鎖終結型で、小さな欠失が14個、小さな挿入が1個、ナンセンス変異が6個ありました。21個の突然変異のうち12個はvan Slegtenhorstら(1997年)によって既に報告されたもので、9個は新しいものであった。変異を持つ家族では、欠失型の変異を受け継いだ3歳の女児を除いて、変異を持つすべての個体が結節性硬化症の正式な診断基準を満たしており、発作もなく、知能も正常で、腹部超音波検査も正常で、身体検査では低メラニン斑のみが認められました。同じTSC1遺伝子変異を持つ7歳の妹は、重度の精神遅滞を抱えていました。研究チームは、TSC1遺伝子変異を有する13人の散発性患者と散発性患者全体のコホートとでは、精神遅滞の発生率と重症度に有意な差がないことを発見しました。この観察結果は、TSC1変異はすべて不活性化するものであることを示し、結節性硬化症-1は散発性結節性硬化症集団のわずか15〜20%にしか発生しないことを示唆しており、また、予兆のある結節性硬化症が発生することを示している。
Jonesら(1999年)は、150人の血縁関係のない結節性硬化症患者とその家族のコホートにおけるTSC1およびTSC2遺伝子の包括的な変異解析を報告した。この解析では、すべてのコーディングエクソンのヘテロ二重およびSSCP解析を行い、パルスフィールドゲル電気泳動、サザンブロット解析、およびロングPCRを用いて大きな再配列をスクリーニングした。150例のうち120例(80%)で変異が検出され、TSC1遺伝子に22例、TSC2遺伝子に98例の変異が認められた。TSC1遺伝子の変異は、散発的な症例では有意に少なかった。TSC1の変異はすべて切断されると予測され、コード化されたタンパク質の構造的またはアダプター的な役割と一致していた。一方、22人の患者に見られたTSC2のミスセンス変異は、主にGAP関連ドメイン(8例)と、エクソン16と17にコードされるヌクレオチド1849と1859の間の小さな領域(8例)に見られ、これらの部位に重要な機能を果たす残基が存在することが示唆された。知的障害は、結節性硬化症-2散発例の方が結節性硬化症-1散発例よりも有意に多かった。
Youngら(1998)は、79人の結節性硬化症患者を対象にTSC1遺伝子の突然変異スクリーニングを行った。患者のうち12名は9q34マーカーとの連鎖を示す家系の患者であった。これらの患者のうち27人にTSC1遺伝子の原因となる突然変異が見つかり、他にも5つの遺伝子の変異が確認された。これらの変異のうち26個は、遺伝子のタンパク質産物の早期終結を引き起こすと予測され、1個はスプライスサイトに変異があった。変異のスクリーニングにより、散発性結節性硬化症の患者では、TSC1の変異が家族性の症例よりも稀であることが示された。これは、TSC1に比べてTSC2の方が重症であることから、結節性硬化症-2の患者の多くが散発性であるという予想と一致する。Youngら(1998)は、Poveyら(1994)の214家系では、家系の1つの枝の重篤な患児のおそらく非浸透性の母親が、家系の他の枝の患児に存在するナンセンス突然変異leu250-to-terを持っていないことを発見した。さらに、その重症男児の祖母は、変異を持たない他の家族との「つながり」であり、その結果、彼女が罹患していると考えられていた単一の鼠径部線維腫は、実際には結節性硬化症の診断ではないという結論に達した。
Aliら(1998年)は、血縁関係のない結節性硬化症患者83人を対象にTSC1の変異を調べた。その結果、83例中16例(19%)に突然変異が見つかった。これらの変異は、塩基置換、小さな挿入、小さな欠失からなり、6つのナンセンス変異、8つのフレームシフト、2つのスプライスサイト変異が生じており、これらの変異はすべて、タンパク質の切断または欠失をもたらすと予想される。TSC1遺伝子座との関連を示した10例のうち8例では、突然変異が見つかった。残りの73例の未同定例では、わずか8つの変異が見つかった(11%)。これらのデータから、Aliら(1998)は、TSC1の突然変異が結節性硬化症の症例の22%を占めると推定している。
Mayerら(1999)は、既知のTSC1の突然変異はすべて、またTSC2のほとんどの突然変異と同様に、タンパク質hamartinとtuberinをそれぞれ切断することを指摘した。Mayerら(1999)は、タンパク質切断テスト(PTT)を適用して、切断変異について両TSC遺伝子の全コード領域をRNAベースでスクリーニングした。TSC2の遺伝子内の大きな再配列を除外するために事前にテストされた48人の未指定TSC患者グループの両TSC遺伝子を同時に調査したところ、TSC1の9例とTSC2の16例で切断変異に起因する異常な移動性ポリペプチドが検出され、TSC2の3例ではタンパク質の肥大化が見られた。TSC1の突然変異には、ナンセンス変異が2つ、挿入が4つ、スプライス変異が3つ含まれていた。TSC2で確認された19の変異は、5人の患者に見られた4種類のナンセンス変異、1つの欠失、1つの挿入、そして12人の患者に見られた少なくとも8種類の変異による7種類のスプライシング異常で構成されていた。原因となる変化を特定できないまま、PTTにより予測された切断変異が追加されたため、TSC1に1例、TSC2に7例が割り当てられました。PTTに異常のない12人の患者は、おそらくTSC2にミスセンス変異があると考えられた。TSC2のスプライシング異常の割合が高いことから、疾患の原因となるイントロン変異の重要性と、その結果を確認するためのRNAベースのスクリーニング法の適用が強化された。Benitら(1999)も同様に、TSC1の完全長のコーディング配列を分析するために、タンパク質切断テストを考案した。PTT と SSCP の組み合わせによる 15 例(散発性 12 例、家族性 3 例)の研究で、彼らは 15 個の変異のうち 5 個を発見しましたが、PTT 単独では 15 個の切断型変異のうち 4 個が検出され、そのうち 2 個は SSCP 分析を逃れました。
Niidaら(1999年)は、家族性40例、散発性86例を含む126名の血縁関係のないTSC患者のTSC1およびTSC2遺伝子の全コーディング領域について、SSCPに続いてダイレクトシークエンスによる変異解析を行ったことを報告しています。その結果、合計74例(59%)で変異が確認され、そのうちTSC1の変異は16例(散発性5例、家族性11例)、TSC2の変異は58例(散発性42例、家族性16例)でした。全体的に見て、この集団ではTSC2の変異が有意に多く見られ、家族性の症例ではTSC1とTSC2の間の変異が比較的均等に分布していたが、散発性の症例ではTSC1の変異が著しく少なかった(p = 0.0035、フィッシャー正確検定)。TSC1の変異はすべてタンパク質を切断すると予測されたが、TSC2では13のミスセンス変異が見つかり、そのうち5つはGAP関連ドメインに集中しており、他の3つはエクソン16に発生していた。知的障害の発生率などの臨床症状を比較したところ、TSC1とTSC2の患者の間に観察可能な違いは見られなかった。
Carbonaraら(1996)は、18人の結節性硬化症患者の20個のハムトーマにおいて、TSC1とTSC2の両遺伝子座と、7つの癌抑制遺伝子を含む領域(p53(191170)、NF1(613113)、NF2(607379)、BRCA1(113705)、APC(611731)、VHL(608537)、MLM(155600))のLOHを調べた。全体として、8つのアンギオミリオリポーマ、8つの巨細胞性星細胞腫、1つの皮質結節腫、3つの横紋筋腫が分析された。TSC遺伝子座のLOHは、散発性(7/14)と家族性(1/4)の両方において、情報提供を受けた患者の大部分に見られた。TSC2遺伝子座のLOHは、散発性患者で統計的に有意に多く見られた(Pは0.01未満)。Carbonaraら(1996)は、最も重度の臓器障害を持つTSC患者の選択に偏りがあったことが、この発見の原因ではないかと考えた。この指摘によると、TSC2の欠損は、早期の腎不全のリスクを高めるか、あるいは巨細胞性星細胞腫の成長を早める可能性があると考えられる。検査した7つのアンションコジーンのいずれもLOHを示さなかったことから、TSC遺伝子のいずれかの産物の欠損が、ハマートマ細胞の成長を促進するのに十分である可能性が示された。同じ患者の星細胞腫と血管筋脂肪腫で異なるマーカーでLOHが観察されたことから、著者らは2回目のヒットの突然変異が多局的に発生していることを示唆した。
Van Slegtenhorstら(1999年)は、225人の血縁関係のない患者のコホートにおけるTSC1遺伝子の突然変異解析を報告した。検出された29個の突然変異のうち、スプライスサイトの突然変異とエクソン7と15の2つのインフレーム欠失を除いて、すべてが切り捨てられたタンパク質につながる小さな変化であった。フレーム内欠失、フレームシフトまたはナンセンス変異を持つ患者の臨床表現型に明確な違いは認められなかった。Van Slegtenhorstら(1999)は、Jonesら(1999)の所見とは対照的に、散発例では明らかに変異が少ないことを発見した。Van Slegtenhorstら(1999)は、結節性硬化症患者全体と比較して、TSC1遺伝子変異を持つ患者の遺伝子型-表現型の相関関係を認めなかった。
Yamashitaら(2000年)は、血縁関係のない日本人結節性硬化症患者27名を対象に、ゲノムDNAのSSCP分析を用いてTSC1およびTSC2遺伝子の変異を調べた。その結果、TSC1には、3つのフレームシフト変異と1つのナンセンス変異を含む、病原性があると考えられる4つの変異が確認された。いずれもhamartin遺伝子の生成物が切断されていることが予想された。著者らは、一連の結節性硬化症-1患者と結節性硬化症-2患者の間で、精神遅滞のリスクに差がないことを見出した。さらに、突然変異によって予想されるタンパク質の切断の程度は、臨床症状の重さとは相関しなかった。
Carbonaraら(1994)は、家族性結節性硬化症の患者に発生した巨細胞性星細胞腫において、結節性硬化症-1の臨界領域におけるヘテロ接合性の喪失(LOH)の証拠を提示した。この腫瘍で失われた9q34ハプロタイプは、正常なTSC1遺伝子を持つことがわかった。これらのデータは、結節性硬化症のハマートマの発生に必要な生殖細胞系および体細胞系の機能喪失突然変異の仮説を支持し、TSC1遺伝子産物の腫瘍抑制作用を示唆している。Greenら(1994)も同様に、TSC1遺伝子の腫瘍抑制作用を示唆する対立遺伝子の欠損を発見した。彼らは、結節性硬化症の散発性症例4例と家族性症例2例から得られた6つのハムトーマを調査したが、いずれも16p13.3上のマーカーの対立遺伝子の欠損を認めなかった。ハマルトーマは、3つの腎血管筋脂肪腫、2つの巨細胞性星細胞腫、および1つの心臓横紋筋腫のパラフィン包埋切片であった。1つの血管筋脂肪腫では、ABO、DBH、D9S66マーカーの対立遺伝子が欠損していた。家族構成から、疾患の病相やマーカー対立遺伝子を決定することはできなかった。この結果は、結節性硬化症-1の9q34への配置を支持し、その遺伝子はD9S149とD9S67の間に配置された。同様の結果から、TSC2遺伝子の成長抑制の役割が支持された。
Greenら(1996)は、非ランダムなX染色体の不活性化研究を用いて、結節性硬化症ハマルトーマのクローン性を証明した。それまでは、9q34のTSC1遺伝子または16p13.3のTSC2遺伝子のいずれかの領域にあるDNAマーカーのLOHが、これらの病変が実際にクローン性であるという結論を裏付けていた。X染色体不活性化の研究では、Greenら(1996年)は、同一患者の正常組織と比較して、保存パラフィン包埋腫瘍から抽出したDNAのX染色体不活性化を分析することにより、女性症例のTSC hamartoma 13例のクローン性を調べた。このうち7例は散発性で、2例は9q34に連鎖した家系から、1例は16p13.3に連鎖した家系から、3例は小さすぎて連鎖による割り当てができない家系からのものであった。13例のハマルトーマのうち、以前にLOHを示したのは4例のみで、1例はTSC1遺伝子の領域に、3例はTSC2遺伝子の領域にあった。PCR法を用いて、Xq11-q12のアンドロゲン受容体トリプレット・リピート多型に隣接するHpaII制限部位のメチル化の違いを解析した。12の病変では、片方のX染色体が完全にメチル化され、もう片方はメチル化されていないという、偏った不活性化パターンが見られた。正常組織では、不活性化のパターンはランダムであった。この発見は、病変部が1種類以上の細胞で構成されていたことから、特に興味深いものと考えられている。
Henskeら(1996)は、TSC1とTSC2領域のLOHについて、47人のTSC患者の87の病変を分析した。血管筋脂肪腫または横紋筋腫を有する28名の患者のうち、12名(57%)の病変で16p13のLOHが検出された。9q34のLOHは1人の患者のみで検出された。著者らは、TSC脳病変のわずか4%にしかLOHが認められなかったことを指摘し、TSC脳病変はTSC腎病変や横紋筋腫病変とは異なる病態メカニズムに起因している可能性を示唆した。
Niidaら(2001年)は、10人の患者から得られた24個のハマルトーマについて、LOH解析、TSC1およびTSC2のSSCPスクリーニング、TSC2のプロモーターメチル化研究、およびクローナリティ解析を含む複数の方法でセカンドヒット変異を解析した。その結果、TSC遺伝子の完全な不活性化は、他のTSC病変ではなく、腎血管筋脂肪腫に特徴的であるという証拠が得られた。
Seppら(1996年)は、結節性硬化症の34症例から得られた51個のハマートマにおけるLOHのスペクトルについて述べている。51個のハムトーマのうち、21個(41%)がLOHを示した。16個のハムトーマがTSC2の周辺でLOHを示し、5個のハムトーマがTSC1の周辺でLOHを示したのである。両方の遺伝子座のマーカーでLOHを示したハムトーマはなかった。Seppら(1996)は、ハマートマの種類によってLOHの頻度に大きな違いはないようだと報告している。LOHは、血管筋脂肪腫17例中7例、巨細胞性星細胞腫9例中5例、線維腫8例中3例、皮質結節5例中3例、そして鮫肌、心臓横紋筋腫、腎癌にも認められた。Seppら(1996)は、染色体16p13.3上のTSC2領域に対するLOHが多いのは、単にTSC1遺伝子座があまり定義されておらず、そのため9q34に対するLOHが見つかりにくいことを反映しているのかもしれないと指摘している。
Bjornssonら(1996年)は6例のTSC関連RCCを調査した。その結果、TSC関連RCCの中には、臨床的、病理学的、遺伝的特徴があり、それが散発性RCCとは異なることが示唆された。臨床的には、TSC関連RCCは散発性腫瘍よりも若い年齢(36歳)で発生し、主に女性に発生した(6例中5例)。Bjornssonら(1996年)は、5つの腫瘍が透明細胞の形態を示し、そのうちの2つは顆粒細胞の組織像に加えて高悪性度の紡錘細胞領域を有していたと報告している。研究対象となった6人の患者のうち、4人は癌で死亡し、3人は後腹膜への転移に加えて肺への転移も認められた。生き残った2名の患者は、腫瘍が偶発的に発見された(1名は血管筋脂肪腫と腎出血の手術時、もう1名は腎嚢胞の手術時)。メラニン細胞関連マーカーであるHMB-45の免疫染色は、6例中4例で陽性であった。LOHは、9q34、16p13.3、および2例では3p染色体に認められた。Bjornssonら(1996)は、9q34のみのLOHを持つ腫瘍は偶発的に発見されたものであり、退形成の特徴を持たないと指摘している。対照的に、9q34と3pのLOHを持つ腫瘍は、退形成の特徴を持ち、転移していた。
Cheadleら(2000)は、結節性硬化症の分子遺伝学的進歩をレビューした。その結果、TSC1遺伝子に変異がある154例とTSC2遺伝子に変異がある292例の報告があった。TSC1遺伝子の変異の47%(73/154例)は一塩基置換で、そのうち82%はナンセンス変異であった。
Daboraら(2001年)は、結節性硬化症のインデックス患者224人を対象とした研究で、186人(83%)に突然変異が見つかり、その内訳は、138の小さなTSC2突然変異、20の大きなTSC2突然変異、28の小さなTSC1突然変異であった。臨床評価によると、TSC1遺伝子変異を有する散発性患者は、同年齢であるにもかかわらず、TSC2遺伝子変異を有する患者よりも平均して病状が軽度であった。発作の頻度が低く、中等度から重度の精神遅滞があり、独立細胞下結節や皮質結節が少なく、重度の腎病変が少なく、網膜ハマートマがなく、重度の顔面血管線維腫が少なかった。変異が認められなかった患者も、TSC2に変異があった患者に比べて、平均して病状が軽度であった。TSC1とTSC2の変異を持つ患者の多くの臨床的特徴には重複が見られたが、いくつかの特徴(グレード2〜4の腎嚢胞または血管筋脂肪腫、額の斑点、網膜の過誤腫、肝臓の血管筋脂肪腫)は、TSC1の患者では非常にまれであるか、全く見られなかった。このように、TSC1では、生殖細胞変異と体細胞変異の両方が、TSC2よりも少ないようです。確定した突然変異のない患者の疾患の重症度が低いことから、これらの患者の多くはTSC2の突然変異のためにモザイクをかけられているか、あるいは臨床表現型が比較的軽度である、まだ確定していない遺伝子座の突然変異のためにTSCを発症していると考えられる。
Langkauら(2002年)は、臨床的にTSCが確認された68人の血縁関係のない非選択的な患者(59人の散発性患者と9人の家族性患者)の遺伝子型を調べ、TSC2遺伝子に29の突然変異、TSC1遺伝子に2の突然変異を同定した。その結果、TSC2遺伝子に29個、TSC1遺伝子に2個の変異が確認された。彼らは、この患者群におけるTSC1-TSC2変異の比率が、連鎖研究に基づいて以前から予測されていた1:1の比率とは大きく異なることを指摘した。彼らは、より軽度の表現型はTSC1遺伝子の変異と関連することが多く、確認を逃れる可能性が高いことを示唆した。
短縮型タンパク質をコードする変異を持つmRNAの多くは、ナンセンス媒介性mRNA崩壊(NMD)を受け、その結果、変異型転写物のレベルが低下する。TSC1の突然変異は、事実上、すべてのタンパク質産物を切断している。Jeganathanら(2002年)は、TSC1のコード化領域および3プライム非翻訳領域の多型を用いて、患者のTSC1転写物レベルを調べるための転写物不均衡アッセイを開発した。この方法により、TSC1とTSC2の患者を対象にしたブラインドテストで、TSC1患者7名中6名を正しく同定することができ、偽陽性はなかった。TSC1のNMDの程度は、家族内の臨床的特徴の違いにかかわらず、個々の変異と相関しており、位置的な偏りを示す強い証拠はなかった。
Auら(2007年)は、結節性硬化症複合体の診断が確定している325人を対象に、突然変異解析を行った。その結果、de novoの72%(257人中199人)、家族性症例の77%(68人中53人)に変異が認められ、TSC1遺伝子に17%、TSC2遺伝子に50%の変異が認められた。分類されない変異が4%、変異が確認されないものが29%あった。プロバンドに観察された結節性硬化症複合体のすべての所見について、遺伝子型/表現型の解析が行われたが、これには過去の2つの大規模研究で解析されなかったいくつかの臨床的特徴が含まれていた(例えば、Sancakら、2005年参照)。Auら(2007)は、TSC2遺伝子変異を有する患者は、TSC1遺伝子変異を有する患者とは対照的に、低メラニン斑と学習障害が有意に多いことを示し、これまでの研究では指摘されなかった所見を示した。また、著者らは、TSC2の変異を持つ人はより重篤な症状を持つことを示唆する2つの類似した研究と一致する結果を観察した。
Nellistら(2009年)は、結節性硬化症の原因となるTSC1遺伝子の8つの異なるミスセンス変異(M224R; 605284.0008、L180P; 605284.0009など)を同定した。In vitroの機能発現研究では、これらの変化によってTSC1のレベルが低下し、免疫ブロッティングで検出されるTSC1依存性のmTOR活性の阻害が減少することが明らかになった。いずれの場合も、機能的な特徴は、遺伝的および表現型の所見と一致しており、ミスセンスの変化が病原性であることを示していた。Nellistら(2009)は、TSC1のN末端に近い部分(アミノ酸117~224)の変異は、TSC1の定常状態のレベルを低下させると結論づけている。
肺リンパ脈管筋腫症
肺リンパ管筋腫症(LAM; 606690)は、肺の平滑筋細胞のびまん性増殖を特徴とする破壊的な肺疾患である。肺LAMは、孤立型(散発性LAM)または結節性硬化症複合体(TSC-LAM)に伴って発症することがある。Satoら(2002年)は、日本人のTSC-LAM患者6人と散発性LAM患者22人のTSC1およびTSC2遺伝子を調べ、6つの新規変異を同定した。TSC2の生殖細胞変異は、TSC-LAM患者6人のうち2人(33.3%)で検出され、TSC1の生殖細胞変異は、散発性LAM患者22人のうち1人(4.5%)で検出された。腫瘍抑制モデルによると、TSC-LAM患者4人中3人と、散発性LAM患者8人中4人のLAM細胞でLOHが検出された。さらに、複数の組織から採取されたLAM細胞では、同一のLOHまたは2つの同一の体細胞変異が認められたことから、LAM細胞はある病巣から別の病巣へと広がることが示唆された。これらの結果は、TSC-LAMには生殖細胞変異があるが、散発性LAMにはない、散発性LAMは2つの体細胞変異を有するTSC2疾患である、様々なTSC変異がLAMを引き起こす可能性がある、という一般的なLAMの病因概念を裏付けるものであった。しかし、本研究は、散発性LAMの一部がTSC1疾患である可能性を示している。したがって、散発性LAMの患者であっても、両方のTSC遺伝子を調べるべきである。
局所性皮質異形成、II型、体細胞
Focal Cortical Dysplasia Type II (FCORD2; 607341)は、大脳新皮質とその下の白質に限局した奇形を特徴とする。TSCで観察されるものと同様のバルーン細胞が多くの症例で見られ、Beckerら(2002)はFCD(bc)と呼んでいる。Beckerら(2002)は、組織学的にFCD(bc)と認定された慢性局所性てんかん患者48名のコホートにおいて、TSC1およびTSC2遺伝子の変化を研究した。DNAは、バルーン細胞、異形成の神経細胞、および隣接する正常な脳組織からの非lesional細胞をマイクロダイセクションおよびレーザーアシストで分離して得られた。FCD(bc)患者では、エクソン5と17に影響するTSC1遺伝子産物のアミノ酸交換とエクソン14と22の無声塩基交換をもたらす配列変化が、200人の対照者と比較して増加していた。また、FCD(bc)と隣接する正常細胞でも配列変化が検出された。24人の患者において、コントロール組織と比較して、ミクロダイセクションされたFCD(bc)サンプルのTSC1遺伝子座におけるLOHを調べるのに適したDNAがあった。11人のFCD(bc)症例でLOHが見つかった。TSC2遺伝子では、コントロールと同程度の頻度でサイレント多型のみが検出された。Beckerら(2002)は、FCD(bc)は、神経放射線学的、神経病理学的、および分子遺伝学的に異なる特徴を持つ臨床病理学的実体を構成していると結論づけ、TSC1遺伝子がその発症に関与し、TSC複合体との間に病因関係があることを示唆している。
Beckerら(2002)は、TSCの脳内病変ではTSC2遺伝子が存在する16p13.3、TSCの脳外病変ではTSC1遺伝子が存在する9q34の対立遺伝子のLOHが観察されていることを指摘しています。局所性皮質異形成におけるTSC1遺伝子に関連するLOHの発見は、がん抑制遺伝子の不活性化に関する2ヒット仮説に関連する可能性がある。TSC1遺伝子座内のLOHと他の対立遺伝子の配列多型の組み合わせが観察されたことから、TSC1遺伝子座内のLOHは、浸透率が低く、発現パターンが著しく制限された素因となる生殖細胞変異として機能していると考えられる。TSC1とTSC2が細胞周期を制御する複合体として働くことを考えると(Potterら、2001年、Taponら、2001年)、このような変異アリルは、脳の発達中の限られた期間に増殖活性を誘導する可能性がある。
Gumbingerら(2009)は、23人のFCDタイプIIを含む33人の局所性皮質異形成患者の遺伝子型-表現型を詳細に解析した結果、患者の病変部の脳組織と血液の両方で、TSC1およびTSC2遺伝子にいくつかの配列変異を同定したが、その頻度は健常者と同程度であったという。ほとんどの配列変化はサイレントであった。Gumbingerら(2009年)は、局所性皮質異形成はTSC遺伝子の変異によって引き起こされるものではなく、TSCの多型によって促進されることもないと結論づけている。
II型FCD(FCORD2;607341)による発作を持つ血縁関係のない子ども4人(IIa型3人、IIb型1人を含む)から切除した脳組織において、Limら(2017年)は、TSC1遺伝子にde novoの体細胞ミスセンス変異(R22W、605284.0010およびR204C、605284.0011)を同定した。これらの変異は、MTOR経路の遺伝子を対象としたシークエンスにより発見されたもので、脳組織での頻度は3%以下と非常に低いものでした。この患者は、脳組織で体細胞のmTOR変異が陰性であったII型FCD患者40人のコホートの一部であった。患者のジストロフィー脳細胞およびTSC1変異体を導入した細胞では、野生型に比べてS6Kリン酸化(RPS6KB1; 608938)が増加しており、mTOR経路の過剰活性化と一致していた。また、変異型TSC1は、TSC2との結合が阻害されており、TSC1-TSC2複合体が破壊されていることがわかった。ラパマイシンで処理することにより、トランスフェクトした細胞での異常なS6Kリン酸化は抑制された。
エベロリムスの感受性
Iyerら(2012)は、mTORC1複合体を標的とした薬剤であるエベロリムス(601231)により、持続的(2年以上)かつ継続的な完全奏効を達成した転移性膀胱がん患者の腫瘍ゲノムを調査しました。Iyerら(2012)は、TSC1遺伝子に2bpの欠失があり、フレームシフト切断が生じていることと、NF2(607379)遺伝子にナンセンス変異があることを明らかにしました。Iyerら(2012年)は、96人の高悪性度膀胱がんの第2コホートで両遺伝子の配列を決定し、TSC1の体細胞変異を5つ追加で確認したが、NF2の追加変異は検出されなかった。その後、Iyer氏ら(2012年)は、TSC1変異が膀胱がんにおけるエベロリムス治療の臨床的有用性を示すバイオマーカーとなるかどうかを検討し、エベロリムス治療を受けた13人の膀胱がん患者を追加調査しました。その結果、TSC1にナンセンス変異を持つ腫瘍が3つ追加され、そのうち2人の患者はエベロリムスに軽度の反応を示した(それぞれ17%と24%の腫瘍退縮)。病勢が進行した9人の患者のうち8人の腫瘍は、TSC1野生型であった。TSC1変異型腫瘍の患者は、野生型腫瘍の患者に比べてエベロリムスの投与期間が長く(7.7カ月対2.0カ月、p=0.004)、再発までの期間も有意に改善した(4.1カ月対1.8カ月、ハザード比=18.5、95%信頼区間2.1~162、p=0.001)。Iyerら(2012)は、腫瘍にTSC1の体細胞変異が存在するがん患者では、mTORC1指向の治療法が最も効果的である可能性があると結論づけています。