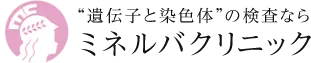承認済シンボル:ALK
遺伝子名:ALK receptor tyrosine kinase
参照:
HGNC: 427
AllianceGenome : HGNC : 427
NCBI:238
遺伝子OMIM番号105590
Ensembl :ENSG00000171094
UCSC : uc002rmy.4
遺伝子のlocus type :タンパク質をコードする
遺伝子のグループ:Receptor tyrosine kinases
CD molecules
遺伝子座: 2p23.2-p23.1
遺伝子の別名
anaplastic lymphoma kinase
anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase
CD246
CD246 antigen
NBLST3
概要
ALK受容体チロシンキナーゼのシグナル伝達過程:
刺激と二量体化: キナーゼは細胞表面で刺激を受け、類似のキナーゼと結合して二量体化します。
リン酸化: 二量体化したキナーゼは、リン酸化と呼ばれる過程でリン酸基でタグ付けされます。リン酸化はキナーゼを活性化する(オンにする)メカニズムです。
シグナル伝達: 活性化されたキナーゼは細胞内の他のタンパク質にリン酸基を転移し、それによってこれらのタンパク質を活性化します。この活性化はシグナル伝達経路を通じて連続して行われます。
細胞プロセスへの影響: これらのシグナル伝達経路は、細胞の成長や分裂(増殖)、成熟(分化)など、多くの細胞プロセスにおいて重要な役割を果たします。
ALK受容体チロシンキナーゼの特定の機能:
ALK受容体チロシンキナーゼの特異的な機能は完全には明らかにされていませんが、発生初期に作用して神経細胞の増殖を制御するのに役立っていると考えられています。このため、ALK受容体チロシンキナーゼは神経系の発達に重要な役割を果たす可能性があります。
疾患との関連:
ALK遺伝子の異常や変異は、特にがんを含むさまざまな疾患と関連があるとされています。例えば、ALK遺伝子の転座は、特定の種類のリンパ腫や肺癌で観察されます。このような疾患において、ALK遺伝子は潜在的な治療標的となり得ます。
総じて、ALK遺伝子およびその産物であるALK受容体チロシンキナーゼは、細胞の発達、成長、および病理において重要な役割を果たすことが示唆されています。
遺伝子と関係のある疾患
{Neuroblastoma, susceptibility to, 3} 神経芽腫感受性3
613014 3
※OMIMにおいて中括弧”{ }”は、多因子疾患(糖尿病、喘息など)や感染症(マラリアなど)に対する感受性に寄与する変異を示す。
神経芽細胞腫の一部の患者において、ALK遺伝子に少なくとも16種類の変異が確認されています。これらの変異は、ALK受容体チロシンキナーゼの単一タンパク質構成要素(アミノ酸)を変化させ、細胞の制御不能な増殖と腫瘍形成に寄与している可能性があります。神経芽細胞腫を含むがんは、細胞の増殖や分化を制御する遺伝子に変異が蓄積することによって発生します。最も一般的な変異の一つは、1275位のアルギニン(Arg1275)がグルタミン(Gln)に置き換わるもの(Arg1275GlnまたはR1275Qと表記)で、これは家族性と散発性の両方の神経芽細胞腫で見つかります。ALK遺伝子の変異や遺伝子増幅は、リン酸化されるために細胞外からの刺激を必要としなくなる変異または過剰発現したALK受容体チロシンキナーゼを生じさせ、これが神経芽細胞腫の発症に寄与する可能性があります。
遺伝子の発現とクローニング
この研究では、予測されたハイブリッドタンパク質において、ヌクレオホスミンのアミノ末端がALKの触媒ドメインに結合していることが示されました。ALKは正常なリンパ球では発現しないが、小腸、精巣、脳で発現しており、キナーゼのインスリン受容体サブファミリーと最大の配列類似性を示しています。この研究から、切断型ALKの予定外の発現が大細胞リンパ腫の悪性化に寄与している可能性が示唆されています。
遺伝子の構造
マッピング
Morrisらの発見: Morrisらは、t(2;5)(p23;q35)転座を用いたポジショナルクローニングを通じて、ALK遺伝子をヒトの染色体2p23上に同定しました。この発見は、大細胞リンパ腫などの特定のがんタイプにおいて見られる特定の染色体転座の背後にある分子メカニズムを理解する上で重要です。
Mathewらの研究: Mathewらは種間戻し交配解析を用いて、マウスのホモログ(同等の遺伝子)をマウスの17番染色体にマッピングしました。また、彼らはマウスの17番染色体遠位部とヒトの2番染色体短腕との間に相同性があることを確認しました。
これらの研究は、遺伝子マッピング技術の進歩とともに、遺伝子の染色体上の位置や構造に関する理解を大きく進展させました。特に、ALK遺伝子の位置の特定は、この遺伝子が関与する疾患の研究において重要な意味を持ちます。ヒトとマウスでの遺伝子のマッピング結果の比較は、遺伝子の進化的保存性や機能についての洞察を提供し、疾患の理解や治療法の開発に寄与することが期待されます。
遺伝子の機能
Leeら(2003年)の研究は、ショウジョウバエの筋肉発生における「Jelly belly」(Jeb)という分泌タンパク質の重要性を示しました。Jebの受容体がショウジョウバエのALKホモログであることが明らかになり、Jeb/Alkシグナルが筋芽細胞融合遺伝子「dumbfounded」(duf)や「org1」の誘導に関与していることが分かりました。
Englundら(2003年)は、ショウジョウバエのAlkが内臓中胚葉におけるJebの受容体であることを示し、JebとAlkの相互作用がdumbfounded(duf)遺伝子の発現を刺激し、筋肉の融合に必要であることを明らかにしました。
Pivaら(2006年)は、ALK陽性ALCLの発現プロファイルを分析し、CEBPBとBCL2A1がALK陽性ALCL細胞の形質転換や増殖、生存に重要であることを発見しました。
Savanら(2011年)は、IL22R1が正常白血球には発現していないが、ALK陽性ALCL患者のT細胞に発現していることを明らかにしました。IL22R1の発現は、IL22、IL17、IL8の増加と関連しており、これらのサイトカインが炎症とALK陽性ALCLに関与している可能性が示唆されました。
Takagiら(2013年)は、アダプタータンパク質SHFがALKと相互作用し、SHFのノックダウンが神経芽腫細胞の移動性と浸潤性を増加させることを発見しました。
Wiesnerら(2015年)は、新規ALKアイソフォーム「ALK(ATI)」を発見し、このアイソフォームが癌細胞の増殖と腫瘍形成を促進することを報告しました。
Majumderら(2021年)は、アルツハイマー病と2型糖尿病モデルマウスにおいて、GRB2およびNOX4のレベルが上昇していることを示し、これらが疾患の発症に関与している可能性を示唆しました。
ALK/EML4融合タンパク質
ALK/EML4融合タンパク質は、非小細胞肺癌(NSCLC)に関連する重要ながんタンパク質です。この融合は、染色体2p内の小さな逆位によって発生し、EML4遺伝子とALK遺伝子の一部が結合して形成されます。
Sodaら(2007)の研究は、この現象を初めて報告し、非小細胞肺癌細胞におけるEML4とALK遺伝子の融合を明らかにしました。この研究では、融合遺伝子を強制発現させたマウス3T3線維芽細胞が形質転換病巣を形成し、ヌードマウスでは皮下腫瘍を生じることが示されました。また、日本人の非小細胞肺癌患者75人中5人(6.7%)にこの融合転写産物が検出され、これらの患者にはEGFR遺伝子の変異はなかったことも報告されました。
この融合タンパク質は、N末端部分がヒトEML4と同一で、C末端部分がヒトALKの細胞内ドメインと同一である1,059アミノ酸から成るチロシンキナーゼです。
Choiら(2010年)の研究では、EML4-ALK融合型チロシンキナーゼが非小細胞肺癌の4~5%に見られること、そしてALK阻害剤による治療の再発期に患者の腫瘍細胞からEML4-ALKのキナーゼドメイン内に2つの二次変異が発見されたことが報告されました。これらの変異は独立して発現し、異なるALK阻害剤に対して耐性を付与しました。
これらの研究は、EML4-ALK融合タンパク質が非小細胞肺癌の発症と進行において重要な役割を果たし、特にALK阻害剤治療に関連する耐性メカニズムの理解に貢献しています。このような知見は、非小細胞肺癌の治療戦略を改善するための基盤となります。
ALK/NPM1融合タンパク質
Zhangらの2007年の研究では、ALK/NPM1融合タンパク質に関する重要な発見がなされました。この研究は、ALKチロシンキナーゼの異所性発現がT細胞リンパ腫(TCL)のサブセットで起こり、これが様々なパートナー、特にNPM1との染色体転座によるものであることを示しました。
研究の主要な発見:
NPM1/ALK融合タンパク質: この融合タンパク質はNPM1のオリゴマー化モチーフとALKの触媒ドメインを含み、自己リン酸化によって構成的に活性化されます。これにより、下流のエフェクター(例えばSTAT3)が活性化され、細胞の悪性形質転換が媒介されます。
STAT5AとSTAT5Bの発現パターン: NPM1/ALKを発現するTCL細胞株はSTAT5Bを発現しているのに対し、通常のT細胞やALK陰性TCL細胞株はSTAT5Aを発現しています。
STAT5A遺伝子のエピジェネティックなサイレンシング: NPM1/ALK陽性T細胞では、STAT5Aプロモーター領域がメチル化されており、これによりSTAT5Aの発現がサイレンシングされます。
プロモーターの脱メチル化による影響: プロモーターの脱メチル化はSTAT5Aの活性化をもたらし、さらにSTAT5AとNPM1/ALK融合遺伝子との結合によりNPM1/ALKの発現が抑制されます。
腫瘍抑制因子としての役割: Zhangらは、STAT5Aタンパク質がNPM1/ALKの発現を阻害することにより、腫瘍抑制因子として機能すると結論付けました。
この研究は、T細胞リンパ腫におけるNPM1/ALK融合タンパク質の役割と、細胞内シグナル伝達経路の調節機構を理解する上で重要な貢献をしています。また、この融合タンパク質と関連するエピジェネティックな調節ががんの発生と進行にどのように影響を与えるかについての知見を提供しています。
分子遺伝学
Janoueix-Leroseyら(2008年)は、神経芽腫の大規模なサンプルに対してゲノムワイドの比較ゲノムハイブリダイゼーション解析を行い、ALK遺伝子座におけるコピー数の増加を繰り返し観察しました。この結果は、ALK遺伝子が神経芽腫の発生に重要な役割を果たしていることを示唆しています。
Chenら(2008年)は、高密度一塩基多型ジェノタイピングマイクロアレイを用いて、ALK遺伝子座がコピー数増加および遺伝子増幅の再発性の標的であることを発見しました。さらに、多くの新規ミスセンス変異を同定し、これらの変異が高リスクの神経芽細胞腫において重要な役割を果たしていることを明らかにしました。
Georgeら(2008年)は、原発性神経芽細胞腫の8%でALK遺伝子の変異が確認され、特にF1174L変異が体細胞変異であることを示唆しました。これらの変異は、インターロイキン-3依存性のマウス造血細胞をサイトカイン非依存性増殖に転換しました。
Bourdeautら(2012年)は、周産期発症の神経芽細胞腫患者と出生後の多巣性発症の神経芽細胞腫患者でALKのヘテロ接合体生殖細胞
突然変異を確認しました。これらの変異は不完全浸透性を示し、腫瘍組織でも同じ変異が見られました。彼らの研究は、特に多巣性腫瘍を有する患者において、ALK変異が神経芽細胞腫の素因として重要である可能性を示唆しています。
これらの研究を通じて、ALK遺伝子の変異が神経芽細胞腫の発生と進行において重要な役割を果たしていることが明らかになりました。特に、ALKのチロシンキナーゼドメインにおける変異は、病態の進行や腫瘍形成に寄与しており、これらの変異を持つ腫瘍はALK阻害剤に対して感受性がある可能性が示されています。したがって、ALKは神経芽細胞腫の治療標的として重要であり、将来的な治療戦略の開発において注目されています。
動物モデル
Chiarleら(2008年)の研究
研究の内容: Chiarleらは、ALKの細胞質ドメインの一部をコードするDNAプラスミドをBALB/cマウスにワクチン接種しました。
観察された効果: このワクチン接種は、局所および全身性のリンパ腫増殖から強力かつ長期間の保護をもたらしました。特に、ALK特異的インターフェロン-γ応答とCD8+ T細胞媒介性細胞傷害性を誘発しました。
治療の応用: 化学療法とワクチン接種の併用により、ALK+リンパ腫に罹患したマウスの生存が有意に延長されました。
Maddaloら(2014年)の研究
研究の内容: Maddaloらは、成体動物の体細胞にCRISPR/Cas9システムをウイルス媒介送達する方法を記述し、EML4-ALK駆動肺がんモデルマウスの作製に応用しました。
腫瘍の特徴: この方法で作製された腫瘍は、Eml4-Alk逆位を保有し、Eml4-Alk融合遺伝子を発現しました。また、ALK陽性ヒト非小細胞肺がんに典型的な組織病理学的および分子学的特徴を示し、ALK阻害剤による治療に反応しました。
研究の意義: この一般的な戦略は、マウスにおけるヒト癌のモデル化能力を大幅に拡大し、他の生物においてもモデル化できる可能性を示唆しています。
これらの研究は、動物モデルを用いたがん研究の新しい方法論や治療戦略を開発する上での重要な進展を示しており、特にがんの分子的理解と個別化治療の開発に貢献しています。
アレリックバリアント
0001 神経芽腫、感受性、3
アルク, arg1275gln
神経芽腫(NBLST3; 613014)を発生する5つの独立した家系において、Mosseら(2008)はALK遺伝子の3824G-A転移を同定し、arg1275からglnへの置換(R1275Q)をもたらした。この変異は不完全浸透性を示したが、218本の正常対照染色体では同定されなかった。この変異は蛋白質のキナーゼ活性化ループで起こり、活性化変異である確率は91%である。1家系では、変異を有する母親が3人の異なる父親から3人の子供に変異を伝え、これら3人の子供はそれぞれ神経芽腫を発症した。
Janoueix-Leroseyら(2008年)は、罹患していない突然変異保有者の母親が、それぞれ異なる父親から罹患した2人の子供に突然変異を伝達した1家族を同定した。
Georgeら(2008年)は、神経芽腫患者においてこの突然変異を同定した。
Chenら(2008年)は、いくつかの神経芽腫腫瘍サンプルにおいてR1275Q置換を体細胞変異として同定した。
Bourdeautら(2012年)は、周産期発症の多巣性神経芽腫患者においてde novo heterozygous germline R1275Q変異を同定した。この変異はいくつかの腫瘍でも認められた。
.0002 神経芽腫, 感受性, 3
アルク, gly1128ala
家族性神経芽腫(NBLST3;613014)を分離する大規模な3世代血統において、Mosseら(2008年)はALK遺伝子のヌクレオチド3383においてGからCへの転座を同定し、コドン1128においてグリシンからアラニンへの置換(G1128A)をもたらした。この変異を持つ5人が神経芽腫を発症したが、数人の保因者は発症しなかったことから、不完全浸透性が示された。この変異はタンパク質のPループに生じ、95%の確率で活性化変異であると考えられた。この変異は218の正常対照対立遺伝子では同定されなかった。
.0003 神経芽腫、感受性、3
アルク, arg1192pro
神経芽腫を分離する2家系(NBLST3;613014)において、Mosseら(2008)はALK遺伝子のヌクレオチド3575においてGからCへの転座を同定し、コドン1192においてアルギニンからプロリンへの置換(R1192P)をもたらした。この変異は不完全浸透性を示した。この変異はタンパク質のβ4鎖に生じ、96%の確率で活性化変異であると予測された。この変異は218本の対照染色体では同定されなかった。
Janoueix-Leroseyら(2008年)は、R1192P対立遺伝子を持つ神経芽腫分離家族を独自に同定した。この3世代血統では、祖母は罹患していなかった。娘は12歳で神経節芽細胞腫を発症し、2人の孫はそれぞれ生後3ヵ月と4ヵ月でステージ4の神経芽細胞腫を発症した。祖母に加え、罹患した孫の両親も罹患していなかった。
Bourdeautら(2012年)は、生後6ヵ月で神経芽腫を発症し、その後6歳までに様々な場所に多発性神経節腫を発症した小児において、ヘテロ接合性の生殖細胞系列R1192P変異を同定した。この突然変異は検査したすべての腫瘍で認められた。しかしながら、この生殖細胞系列変異は、患者の母親を含む罹患していない家族3人にも認められ、不完全浸透性を示した。
.0004 神経芽腫、感受性、3
ALK, THR1151MET
神経芽腫患者(NBLST3;613014)において、Georgeら(2008)はALK遺伝子の3452C-T転移を同定し、ALKのキナーゼドメインのコドン1151(T1151M)においてスレオニンからメチオニンへの置換をもたらした。