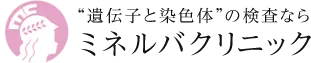SDHB遺伝子
SDHB遺伝子産物は、鉄硫黄クラスター結合活性とユビキノン結合活性を持つと予測。好気呼吸および呼吸性電子輸送鎖に関与すると予測。ミトコンドリア、核膜、細胞膜に存在。Carney-Stratakis症候群、消化管間質腫瘍、ミトコンドリア複合体II欠損症、傍神経節腫、褐色細胞腫に関与。
承認済シンボル:SDHB
遺伝子名:succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B
参照:
HGNC: 10681
遺伝子OMIM番号
Ensembl :
AllianceGenome : HGNC : 10681
遺伝子のlocus type :タンパク質をコードする
遺伝子のグループ:Mitochondrial complex II: succinate dehydrogenase subunits
遺伝子座: 1p36.13
SDHB遺伝子の機能
この癌抑制遺伝子は、ミトコンドリアで重要な役割を果たすコハク酸デヒドロゲナーゼ(SDH)酵素複合体の鉄-硫黄タンパク質サブユニットをコードしている。SDH酵素複合体は核にコードされた4つのサブユニットで構成されている。この酵素複合体はコハク酸をフマル酸に変換し、クエン酸サイクルの一部として電子を放出する。この酵素複合体はさらに、放出された電子が酸化的リン酸化経路に移動するための付着部位を提供する。SDH酵素複合体は、低酸素誘導因子1(HIF1)転写因子を安定化させる酸素センサーであるコハク酸の変換を通じて、酸素関連遺伝子の制御に関与している。この遺伝子に散発性および家族性の変異があると、傍神経節腫、褐色細胞腫、消化管間質腫瘍が生じることから、ミトコンドリアの機能障害と腫瘍形成との関連が支持されている。この遺伝子の変異は、核内4型ミトコンドリア複合体II欠損症にも関与している。2022年6月、RefSeqより提供。
SDHB遺伝子の発現
心臓(RPKM 84.5)、腎臓(RPKM 76.7)、その他25の組織でユビキタスに発現
SDHB遺伝子と関係のある疾患
※OMIIMの中括弧”{ }”は、多因子疾患または感染症に対する感受性に寄与する変異を示す。[ ]は「非疾患」を示し、主に検査値の異常をもたらす遺伝的変異を示す。クエスチョンマーク”? “は、表現型と遺伝子の関係が仮のものであることを示す。
Gastrointestinal stromal tumor 消化管間質腫瘍
606764
AD(常染色体優性), IC 3
胃腸間質腫瘍(GIST)は、染色体4q12上のKIT遺伝子(164920)のヘテロ接合性の生殖細胞系列変異によって起こりうる。GISTはKIT遺伝子の体細胞変異を有する患者にも認められる。
染色体1p36上のSDHB遺伝子(185470)および染色体1q23上のSDHC遺伝子(602413)の生殖細胞系列変異によるGISTのまれな症例が報告されている。
消化管間質腫瘍は、消化管において蠕動運動を制御するペースメーカー細胞であるカハール間質細胞から発生する間葉系腫瘍である。GISTの約70%は胃、20%は小腸に発生し、食道、結腸、直腸に発生するのは10%未満である。GISTは通常、他の消化管肉腫よりも細胞性が強い。GISTは主に40~70歳の患者に発生するが、まれに若年者にも発生することがある(Miettinen et al. 1999)。
GISTはまた、神経線維腫症-1(NF1;162200)およびGIST-plus症候群(175510)など、いくつかの症候群の特徴としてもみられる。
臨床的特徴
西田ら(1998)は、4世代にわたる7人に多発性GISTがみられた日本人家族を報告した。遺伝は常染色体優性遺伝であった。ほとんどの腫瘍は良性であったが、1人の患者は悪性のGISTであった。2人に会陰部の色素沈着がみられたと報告されている。Nishidaら(1998年)は、el-Omarら(1994年)によって報告された、おそらくGISTであろうと思われる複数の腫瘍を有する女性にも会陰部皮膚の色素沈着がみられたことを指摘している。さらに、Marshallら(1990年)は、皮膚または全身性の肥満細胞症(154800を参照のこと)を伴う良性GISTに罹患した家族が複数いることを報告している。
Isozakiら(2000年)は、十二指腸および空腸に1~8cmの巨視的GISTが多発した67歳と40歳のフランス人母子を報告した。検査された腫瘍はすべて悪性度が低く、両患者とも転移を認めなかった。
Beghiniら(2001年)は、父と息子を含む3世代にわたる4人に多発性色素斑がみられたイタリアの家族を調査した。父子ともに、顔面、体幹、四肢および粘膜の皮膚に、ピンポイントの点から5mmまでの大きさの暗褐色の斑点が多数分布していた。18歳の時、父親は腸管神経叢のびまん性過形成を伴う多発性GISTを発症した;検査した腫瘍はすべて良性または悪性度の低いGISTであった。プロバンドの14歳の息子は、皮膚病変の評価を受け、組織学的に真皮上層および中層の血管周囲に円形から卵形の肥満細胞が密に詰まった一群を認めた;彼は蕁麻疹色素変性症と診断された(154800参照)。
Coffeyら(2007年)は、メネトリエ病(137280)およびGISTの臨床的特徴、病因、および分子的治療について概説している。
Mitochondrial complex II deficiency, nuclear type 4 ミトコンドリア 複合体II欠損症, 核型4
619224
AR(常染色体劣性) 3
ミトコンドリア複合体II欠損症核4型(MC2DN4)は、白質脳症を伴う早期発症の進行性神経変性を特徴とする重篤な常染色体劣性疾患である。神経変性の急性エピソードは、しばしば感染や絶食などの異化ストレスによって誘発される。
臨床的特徴
Alstonら(2012)は、血縁関係のある両親から生まれた、神経学的障害、白質脳症、およびミトコンドリア複合体II欠損症の生化学的証拠を有するアジア人の女児を報告した。患者は1歳から発達退行を示した。低身長で関節拘縮があり、4歳で車椅子生活となった。脳MRIでは、深部白質に白質ジストロフィーがみられ、脳梁に信号異常がみられた。MRスペクトロスコピーでは、ジストロフィー白質に乳酸の増加とコハク酸の増加が認められた。
Vanderverら(2016)は、血縁関係のある両親から生まれたトルコ人の男児(患者LD_0756.0A)で、出生時から運動遅滞があり、生後7ヵ月で急性脱力したことを報告した。彼には運動失調、筋緊張低下、痙縮がみられた。3.5歳時の脳MRIでは、U線維を温存したテント上白質に異常信号が認められ、脳梁が腫脹し、脳幹の小脳白質に病変がみられた。
Helmanら(2016)は、5人の患者における臨床的およびX線学的特徴を報告しており、そのうちの4人(患者10、11、16および19)は生存しており、年齢範囲は19ヵ月から9歳で、そのうち1人は呼吸不全により1歳で死亡した(患者15)。症状発現年齢は出生から18ヵ月であった。生後2年以内にMRI検査を受けた4例では、全員に脳梁と視床核の病変、3例に中小脳小節と大脳の病変、3例に脊髄の病変、3例に皮質脊髄路の病変、2例に小脳白質の病変がみられた。患者10は痙性四肢麻痺で認知機能は正常であった。患者11は拡張型心筋症で、著しい肥大と機能低下、拘縮を伴う粗大運動障害、認知は無傷であった。患者16は痙性片麻痺で、重度の運動障害と重度の認知障害があった。患者19は全身性の筋緊張低下、姿勢制御の欠如、過敏性、中等度の認知障害を有していた。
Gronborgら(2017)は、複合体II欠損症の無関係な2人の患者を報告した。患者1は、血縁関係のある両親から生まれたレバノン人の女児で、生後1年目にわずかな発達遅延と筋緊張低下がみられた。その後、12ヵ月齢から発達のマイルストーンが徐々に低下し、それは感染症時に顕著であった。15ヵ月時には、四肢の筋緊張低下と反射亢進がみられた。軽度の両側視神経萎縮、視力低下、オプソクローヌスを伴う水平眼振がみられた。16ヵ月時の脳MRIでは、前頭葉、後頭葉、後側頭葉の白質に信号強度が認められ、側頭葉線維は温存されていた。臨床検査では、血中乳酸値の上昇、尿中のケトン体およびクレブスサイクル中間体(特にコハク酸)の増加が認められた。彼女は呼吸器感染による多臓器不全のため25ヵ月で死亡した。患者2は、非血縁の両親から生まれた男児で、子宮内発育遅延があり、出生時の頭囲、体長、体重が減少していた。生後6ヵ月から、獲得能力の低下が進行し、感染時に悪化した。生後9ヵ月で肺炎を起こし、人工呼吸を必要とする呼吸不全となり、発達能力はさらに低下した。臨床検査では、血中乳酸値の上昇、ALATとASATの上昇、クレアチンキナーゼの上昇、INRの上昇がみられた。左心室の中隔と後壁の重度の拡張と肥大を伴う心筋症であった。生後11ヵ月時のMRIでは、前頭葉、後頭葉、後側頭葉の白質に信号強度が認められ、側頭葉線維は温存されていた。生後1歳になるまで、若干の改善とともに安定していたが、多臓器不全と心停止により死亡した。
Kaurら(2020)は、1歳時にマイルストーンの退行を認めたインド人男児を報告した。生後18ヵ月で熱性発作を発症した。診察では、四肢の緊張が亢進し、深部腱反射が亢進していた。眼科検査で両側視神経萎縮が認められた。脳MRIでは、脳室周囲白質、脳梁、背内側胸膜、脳幹、脊髄に集簇性病変を認めた。血漿および髄液の乳酸値が上昇した。
Paraganglioma and gastric stromal sarcoma パラガングリオーマと消化管間質腫瘍
606864
3
パラガングリオーマおよび胃間質肉腫は、染色体1p36上のSDHB遺伝子(185470)、染色体1q23上のSDHC遺伝子(602413)、および染色体11q23上のSDHD遺伝子(602690)の生殖細胞系列変異によって引き起こされる。
臨床的特徴
CarneyとStratakis(2002年)は、5つの非血縁家系から12人の患者(男性7人、女性5人)が傍神経節腫と胃間質肉腫に罹患したことを報告した。この疾患は常染色体優性遺伝するようであり、不完全浸透率であった。7例が傍神経節腫、4例が傍神経節腫と胃間質肉腫、1例が胃間質肉腫であった。腫瘍は多中心性(傍神経節腫)、多病巣性(胃間質肉腫)、早期発症であった。患者の平均年齢は23歳であった。これらの観察に基づき、著者らは、胃肉腫と傍神経節腫からなる家族性症候群が存在し、Carney triad(604287)とは区別して考えるべきであることを示唆した。
Boccon-Gibodら(2004年)は、腹痛を訴え、Zuckerkandl器官の傍神経節腫の外科的切除を受けた12歳の男児を報告した。翌年、13歳の一卵性双生児に肝転移を伴う胃間質腫瘍が見つかり、化学療法に続いて外科的切除と放射線療法を受けた。双子はともに18歳の時点で生存しており、1人目は明らかに病気がなく、2人目は肝および腹膜病変が安定しており、傍神経節腫の所見はなかった。両親と姉には腫瘍やその他の異常な病歴はなかった。著者らは、この症例がCarney-Stratakis二卵性である可能性が高いことを示唆した。
Paragangliomas 4 パラガングリオーマ4
115310
AD(常染色体優性) 3
家族性傍神経節腫-4(PGL4)は、染色体1p36上のコハク酸デヒドロゲナーゼの鉄硫黄サブユニットをコードするSDHB遺伝子(185470)のヘテロ接合体変異によって引き起こされる。
臨床的特徴
BogdasarianおよびLotz(1979年)は、罹患者が多発性のカテコールアミン分泌性頭頸部傍神経節腫および後腹膜褐色細胞腫を有する家族を報告した。
Glowniakら(1985年)は、3世代にわたる3人が右腎門の褐色細胞腫を有する家系を報告した;これらの患者のうち1人は転移性疾患であった。その前の2世代では、16歳で急死した高血圧の女児を含む3人に褐色細胞腫が疑われた。この血統には、常染色体優性遺伝の仮説に従った義務的保因者がいたが、その保因者は52歳で、CTスキャンや放射性ヨウ素標識メタヨードベンジルグアニジンによるシンチグラフィーを含むいかなる検査でも褐色細胞腫の徴候を示さなかった。Glowniakら(1985年)は、大動脈分岐部にみられるクロマフィン組織の塊であるZuckerkandl器官の褐色細胞腫を有する兄弟姉妹を記載したCookら(1960年)、および下部尿路を含む褐色細胞腫を有する母子を記載したSpringおよびPalubinskas(1977年)の報告に言及した。Glowniakら(1985年)は、原発性副腎外褐色細胞腫は別個の遺伝的実体であることを示唆した。
Pritchett(1982)およびJensenら(1991)は、頸動脈小体腫瘍と副腎および副腎外褐色細胞腫の家族性併発を報告した。
Skoldbergら(1998年)は、連続する3世代のメンバーが髄外褐色細胞腫(家族性クロマフィンパラガングリオーマ)を有するスウェーデンの家族を報告した。第1世代の罹患女性は、甲状腺と膀胱にパラガングリオーマを有していた。甲状腺中毒症は59歳で診断された;彼女は甲状腺中毒症に伴う急性心不全のため69歳で死亡した。この女性の娘には後腹膜と頸部に傍神経節腫があり、孫には2個の後腹膜傍神経節腫があった。2人の女性からの伝播により、この病態は、父親からのみ遺伝する刷り込みを示すPLG1とは区別された。VHL遺伝子(608537)およびRET遺伝子(164761)には変異が認められなかった。
Youngら(2002年)は、1972年に転移性カテコールアミン分泌性傍神経節腫と診断された男性を報告した。彼は、再発性のズキズキする頭痛、動悸、発汗、不安などのカテコールアミン過剰の徴候を呈した。高血圧、尿中カテコールアミンおよび総メタネフリンの排泄増加がみられた。開腹手術により3個の傍神経節腫が同定された:2個は大動脈周囲、1個は副腎に隣接していた。その後、膵頭後方、横隔膜下、肝臓内、大腿骨、胸郭にも傍神経節腫があることが判明した。2002年には元気であった。彼の27歳の息子も副腎外カテコールアミン分泌性傍神経節腫を発症した。
Vanharantaら(2004年)は、推定患者が28歳で転移性腎明細胞がん(RCC;144700)と診断された家族を報告した。患者の母親は心臓内に悪性PGLを有していた。この患者とその母親はともにSDHB遺伝子にヘテロ接合性の生殖細胞突然変異(185470.0006)を有しており、両患者の腫瘍組織では野生型SDHB対立遺伝子のヘテロ接合性の消失(LOH)が認められた。血縁関係のない家族では、2人の兄弟がPGLを発症し、20代でRCCを発症した。兄弟姉妹はいずれもSDHB遺伝子にヘテロ接合性の生殖細胞系列変異(185470.0005)を有しており、1人の患者のPGL組織と2人のRCC腫瘍組織はいずれも野生型対立遺伝子の体細胞性LOHを示した。50歳以前に診断された35の腎細胞がんではSDHB遺伝子変異は同定されなかった。
Timmersら(2007年)は、SDHBに関連した腹部または胸部のPGL患者29人(男性16人)における所見を検討した。PGLは多くの場合、カテコールアミン過剰というよりもむしろ腫瘍の腫瘤効果に関連した症状を呈する、一見散発性のPGLであった。生化学的表現型はノルエピネフリンおよび/またはドーパミンの分泌過多が優勢であったが、腫瘍の10%は生化学的に無症状であった。腫瘍の臨床的発現は遺伝子型では予測できなかった。
Timmersら(2007年)は、SDHBに関連した腹部または胸部のPGL患者29人(男性16人)を調査した。診断時の平均年齢は33.7±15.7歳であった。腫瘍に関連した疼痛は患者の54%に認められ、14%では唯一の症状であった。76%に高血圧があり、90%にPGLの家族歴がなかった。1つを除くすべての原発腫瘍は副腎外から発生した。平均±SD腫瘍径は7.8±3.7cmであった。この紹介ベースの研究では、28%が転移性病変を呈し、1人を除く全員が最終的に2.7±4.1年後に転移を生じた。10%がさらに頭頸部PGLを有していた。生化学的表現型は、ノルエピネフリンとドーパミンの両方の分泌亢進が46%、ノルエピネフリンのみが41%、ドーパミンのみが3%であった。SDHB関連PGLは多くの場合、カテコールアミン過剰というよりもむしろ腫瘍の腫瘤効果に関連した症状を呈する、一見散発性のPGLである。主な生化学的表現型はノルエピネフリンおよび/またはドーパミンの分泌過多であるが、腫瘍の10%は生化学的に無症状である。Timmersら(2007年)は、これらの腫瘍の臨床的発現は遺伝子型では予測できないと結論づけた。
Armstrongら(2009年)は、SDHB遺伝子のヘテロ接合性生殖細胞系列欠失を有する、傍神経節腫/神経芽細胞腫の複合型(256700)を有する13歳の女児を報告した。彼女は当初、切除された腫瘍の組織学的検査で傍神経節腫の特徴を有する副腎外褐色細胞腫であることが判明したが、さらなる解析で分化神経芽細胞腫の形態を有する領域が認められた。著者らは、Casconら(2008年)によって報告された、副腎神経芽腫とSDHB遺伝子の部分欠失(185470.0017)を有する患者について言及した。Armstrongら(2009年)は、傍神経節腫と神経芽腫の両方が神経堤からの共通の胚発生を示すことを指摘しており、これは彼らの患者で同定された複合組織学的腫瘍を説明するかもしれない。
Schimkeら(2010年)は、傍脊椎傍神経節腫を有する2人の成人きょうだいを報告した。この家族が注目されたのは、Fairchildら(1979)によって以前に報告された死亡したきょうだいが、乳児期に神経芽細胞腫、若年成人期に褐色細胞腫と一致する転移性副腎外交感神経傍神経節腫、成人期に腎細胞がんを有していたためである。Fairchildら(1979年)は、同一患者におけるこれらの癌の発生が特異的であることを指摘した。さらに、これらの兄弟のいとこに、転移性腎細胞がんで死亡した者がおり、良性の傍大動脈PGLの病歴があった。遺伝子解析の結果、SDHB遺伝子のヘテロ接合体変異(V140F;185470.0016)が同定された。罹患していない家族が2人いたことから、浸透率の低下または “leaky “変異が示唆された。Schimkeら(2010)は、この遺伝性疾患の病因解明における家族歴の重要性を指摘している。
Heestermanら(2013年)は、MRIでスクリーニングした17人の無症候性SDHB遺伝子変異保有者のうち2人(11.8%)に潜伏性傍神経節腫が認められ、その両方が迷走神経体腫瘍であった。SDHB変異保因者1人は交感神経傍神経節腫であった。
Rijkenら(2016年)は、6人がPGL4であったオランダの多世代にわたる大家族を報告した。3人に褐色細胞腫がみられ、うち2人は悪性であった;1人に頸動脈小体PGL、1人に頸鼓膜PGL、もう1人に副腎外PGLがみられた。不完全浸透性の証拠があった。
Pheochromocytoma 褐色細胞腫
171300
AD(常染色体優性) 3
褐色細胞腫はカテコールアミン分泌腫瘍であり、通常は副腎髄質内に発生する。約10%は副腎外交感神経節に発生し、「傍神経節腫」と呼ばれる。約10%が悪性で、約10%が遺伝性である(Maher and Eng, 2002; Dluhy, 2002)。
Bolande(1974年)は神経クリストパシーの概念と呼称を導入し、褐色細胞腫および甲状腺髄様がんを含む「単純型」と、NF1およびMEN2を含む「複雑型」の神経クリストパシーおよび神経クリストパシー症候群を同定した。
KnudsonとStrong(1972)は、Knudsonの2変異理論を褐色細胞腫に適用し(180200の考察を参照)、適合すると結論づけた。
MaherおよびEng(2002年)は、褐色細胞腫に関連する臨床像および遺伝子を概説した。
臨床的特徴
家族性褐色細胞腫は、CalkinsとHoward(1947)によって最初に報告された。
Hadorn(1963年)は、3人の兄弟が褐色細胞腫と一致する副腎腫瘍を有するドイツ人家族を報告した。兄弟姉妹は頻脈、発汗、高血圧、およびアルブミン尿に苦しんでいた。姉は高血圧性網膜症が進行し、兄はうっ血性心不全であった。剖検の結果、姉は脳出血と両側副腎皮質腫瘍を認めた。生存していた兄弟も同様の症状を呈した。レギチンテストは強陽性で、尿には多量のノルエピネフリンが含まれ、気腹では副腎と傍神経節組織を含む右副腎の腫大が認められた。
Engelmanら(1968)は、家族性褐色細胞腫は通常両側性であり、患者はチラミンの血管圧受容体作用に対する抵抗性を示しやすいと指摘した。
Swintonら(1972年)は、父と息子を含む4人が褐色細胞腫を有する家族を報告した。彼らは、関連した高カルシウム血症はカルシトニン様物質の分泌によるものである可能性を指摘した;高カルシウム血症は副腎摘出術によって改善されうる。
KaufmanおよびFranklin(1979年)は、褐色細胞腫の7症例およびその他の可能性のある症例を有する家族を報告した。
大野ら(1982年)は、父親も褐色細胞腫であった2人の姉妹に褐色細胞腫を観察した。姉妹のうち1人は無虹彩症であり、彼女の褐色細胞腫は悪性であった。
Toledoら(2015年)は、6世代家族から褐色細胞腫を発症した11人を追跡調査した。診断時の年齢中央値は43歳であった。2人は無症状で、9人は平均29歳(範囲10~55歳)から症状が出現した。腫瘍は5例に多中心性、5例に両側性であった。半数以上が10mm未満の副腎髄質結節を少なくとも1個有していた。傍神経節腫、遠隔転移、またはその他の症状は報告されなかった。